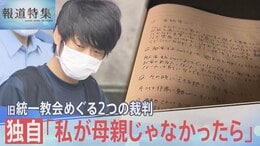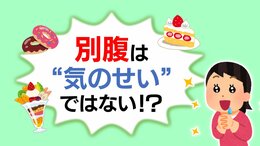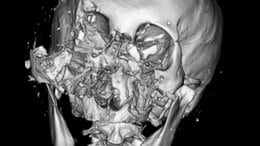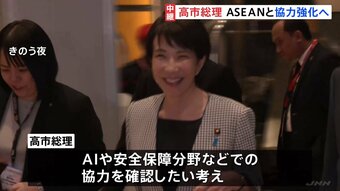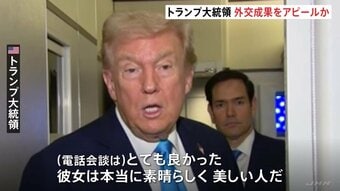悪いとは思っていましたが、ここまで悪いとは思いませんでした。年率換算でマイナス2.1%というGDPの衝撃の数字は、今後の経済運営にも影響を与えそうです。
7-9月期のGDPは前期比年率マイナス2.1%
内閣府が発表した7―9月期GDPは、物価上昇分を除いた実質で前期比0.5%のマイナスでした。これを年率換算すると2.1%もの大幅なマイナスです。マイナス成長は23年10-12月期以来3期ぶりのことです。
日本のGDPは、コロナ禍からの経済正常化によって、今年1-3月期に+0.9%、4-6月期に+1.0%と、高い成長が続いてきました。このため、今期はその反動によるマイナスが予想されていましたが、これほど大きなマイナス幅を予想した専門家はいなかったように思います。
マイナスに最も大きく寄与したのは、民間在庫変動で、寄与度はマイナス0.3と、マイナス分の6割を占めています。自動車輸出が堅調だったことが逆に在庫の減少につながりました。在庫が減ること自体は必ずしも経済の悪化を示すものではありませんし、この在庫変動を除けば、GDPのマイナス幅は0.2%程度、年率換算でも0.8%程度ですから、直ちに不況を心配するような数字ではありません。
個人消費も、設備投資も、「総崩れ」
しかし、肝心の需要面の中身を見ていくと、実は不安材料だらけです。最大の支出項目である個人消費はマイナス0.04%と前期のマイナス0.9%に続く2期連続のマイナスです。消費正常化で街は賑わっていますが、全体として見れば、長引く物価高で、消費は春からずっと実質マイナス、ということになります。
企業の設備投資もマイナス0.6%と2期連続の減少、シリコンサイクルから来る半導体関連の投資が落ち込みの大きな要因です。好調だった住宅投資も5四半期ぶりのマイナスです。資材価格の高騰が設備導入や住宅着工にブレーキをかけている面がある上、投資をしても人手不足で稼働の目処が立たないために、新規投資を手控えるといった例もあるようです。
こうして見てみると、個人消費、設備投資、住宅と、内需は「良いところなし」「総崩れ」の状態です。とても先行きを楽観できるような内容ではありません。