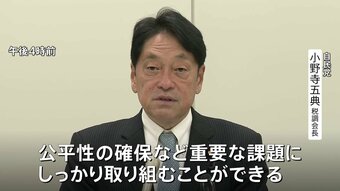大阪でカジノを含む統合型リゾート(IR)が2030年開業をめざして動いています。そうした中、ギャンブル依存症になる人の増加が危惧されています。これに関連して今回は、NPO法人全国ギャンブル依存症家族の会が主宰している「ギャンブル依存症家族のための勉強会」を取材しました。
ギャンブル依存症の家族の苦しみとは
ギャンブル依存症は、賭けごとにのめりこんで抜け出せなくなり、精神の不調や多重債務、借金返済のため窃盗などを繰り返すことのある疾患のひとつです。個人の意思や性格の問題と考えがちですが、全国ギャンブル依存症家族の会はこれを脳から出るドーパミンという物質の機能不全の症状ととらえ、病気に対する知識を増やそうと毎月「勉強会」を開催しています。
そして依存症の人の周囲にはトラブルに巻き込まれ苦しむ家族がいます。そうした依存症の夫や子供をもつ家族が連帯し、情報共有や支援を行うために、2016年、家族の会が設立されました。地域連携、情報提供、今、困っている人への伴走支援の3つを柱に活動し、自傷や希死念慮などの危険な徴候のある人はすぐ入院できるように専門病院と連携しています。全国の都道府県に35の家族会があり、約1000人の会員がいるそうです。
今回取材した東京家族会が主催する「勉強会」は毎回100人程度が参加し、取材した日は出席者88人、初めての参加者が5人いました。
前半に、ギャンブル依存症の当事者、回復した人や問題解決に近づいた家族などが体験談を講演します。そのあと参加者による解決策のマニュアル本の読み合わせがありました。参加者が声を出して読むことで解決策が明瞭に頭に入るように思いました。
そして後半には1時間程度、参加者がいくつかのグループに分かれて体験談を話し合うミーティングが行われます。東京家族会の会員・宇都宮美貴さんに、どんな相談が多いか聞きました。

東京家族会の会員・宇都宮美貴さん
「夫や子供からお金の無心があって、その都度借金の尻拭いを何回も繰り返してきたんだけれど、どうしたらいいですかという相談が一番多いかなと。我が家の場合は32歳の夫がギャンブル依存症で、結婚する時に多額の借金があることがわかりました。そのまま結婚しましたが、家庭内窃盗と呼ばれるような、出産祝いを使い込まれたりとか、家の中の貴重品を勝手に売られたり、借金のたびに尻拭いをしてしまったり、トラブルがつきまとっていました。そこで2年半前にNPO法人全国ギャンブル依存症家族の会につながって、どう対応するべきなのか教えてもらいました。たとえばわが家では最終的に闇金にお金を借りるところまでいきましたが、私に闇金から連絡が来たときの具体的な対応など、そういう所まで支援してもらいました。その後、夫はグレイス・ロードという回復施設に17か月入寮して卒寮し、現在は当会の当事者支援部として活動しています」
ミーティングの様子を見ていましたが、今回、初めて勉強会に参加して、夫が借金を繰り返す悩みを泣きながら訴えていた人が、同じ経験をしてきた人たちの「それは"あるある"です」という言葉に笑顔になったり、もっとひどい経験をした人の話にびっくりしたり、話の輪の中で明るい表情に変わっていくのが印象的でした。
勉強会に参加して、救われた
取材した日、講演を行った茨城家族会の荒木玲奈さんも、のちに離婚する夫が依存症で、荒木さんが380万円、彼女の父が300万円も借金を肩代わりしたのに、それでもギャンブルをやめなかったそうです。 荒木さんは1年半ほど前に家族の会につながり、勉強会に参加したことで自分が変わり、救われたと言っています。

茨城家族会の荒木玲奈さん
「今日、久々に会う方もいたんですけど、あの時暗かったよねという感じで、本当に印象が変わったねというふうに言ってもらえて。表情も明るくなったし、話し方とか全部変わったんだなと言われて気づきました。やっぱり同じ境遇を経験した方々の話を聞くと、一人じゃないんだなって、今まで誰にも言えなかったことだったので、そこは共感と慰めというのもすごく大きくて、それだけで安心できました。私の酷い体験が、今困ってる方の何か役に立ったり、ヒントになったり、聞いてもらうことによって役に立つと感じられるので、語ることが、無駄じゃなかったのだな、というのをすごく感じますね。ひとりで悩みを抱えずに、どこかに助けを求めることが第一、ギャンブル依存症の問題は家族だけでは解決できないので、外部に助けを求めるのは大切な一歩かと思います」
同じように、家族に問題を抱えている会員の松本敦子さんは次のように語っています。
会員の松本敦子さん
「息子が28歳で依存症で、いろいろ問題を起こしまして、今は回復施設にいるんですが、親として間違った対応をしないよう、正しい知識を得るために、こちらの会につながるようアドバイスをいただいて、入会しました。ギャンブル依存症の方たちはたどる道が似てたりするので、経験者の今までの経緯などを聞いて学べるというところと、自分の話に共感してもらえることがすごく大切で、勉強になります。息子は今、2回目の回復施設に入寮中なんです。回復施設で、仲間の中で回復を続けていると思います。どんなふうに過ごしているかは分かりませんけども、息子の回復を信じて、私も対応を間違えないように頑張ります。息子は仲間の中で回復して、私もこの会の仲間の中で学んで回復してくことが大事かなと思ってます」