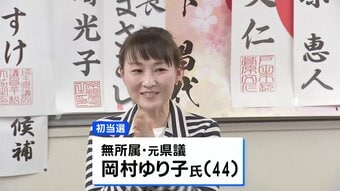国土強靭化に4兆円、投資促進に3兆円
最大の支出項目は、国土強靭化などへの取り組みの4兆2827億円です。
何のことはない、経済対策の多くが、相も変わらず、ダムや道路といった公共事業に使われるのです。
中長期的に防災・減災への取り組みを進める必要があるにしても、人手不足や資材高騰が進む中で需要刺激を急ぐ必要などなく、むしろ供給制約を強めかねません。
次の支出項目は、国内投資促進のための3兆4375億円です。このうち半導体や生成AI(人工知能)関連への支援が2兆円にのぼります。
先端半導体の製造を目指すラピダスの試作ラインや、TSMCの第2工場建設への補助金も含まれています。
戦略産業への投資促進は、もちろん今後の雇用や所得の増加につながりますが、今求められている物価高や賃上げに即効性があるわけもなく、経済対策を機に、重点施策に一気に上積みを図るという霞が関お得意のパターンです。
この他、▼人口減少を乗り越える対策、▼中堅・中小企業や地方の成長のための対策に、それぞれ1兆円以上と、いわば構造的な問題への対応策が並びます。
結局のところ、今の物価高や、今の賃上げといった国民が求めていた対策は補正予算のわずか一部に過ぎません。
議論と実際の支出割合は、全く釣り合っていません。
岸田政権が決定した経済対策や補正予算案が、いかに総理の「掛け声」とは異なっているかがわかります。
結局、財源の7割が国債
その一方で歳入、つまり補正予算の歳入をみると、補正予算13兆円余りのうち、8兆8750億円は新規の国債発行で対応します。
要は7割近くを借金で賄うことになります。23年度の税収の上振れ分は、わずか1710億円しかありません。
岸田総理が「税収増」とか「還元」とかという言葉を繰り返したため、まるで余裕があるように聞こえますが、今現在、予想外の税収増が発生しているわけではないのです。
鈴木財務大臣は、8日の国会答弁で、過去の税収増はすでに支出されており、還元する財源があるわけではない、との認識を示しました。
このこと自体は目新しい事実ではありませんが、この時期に財務大臣が、岸田総理が説明してきた「還元論」を明確に否定する答弁を行ったことから、財務省がついに岸田政権を見限ったか、との受け止め方も出ています。
黄昏感漂う岸田政権。岸田総理には、宏池会出身の総理大臣らしく、もっとまっとうに経済政策に向き合って欲しかったと、思わずにはいられません。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)