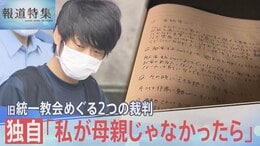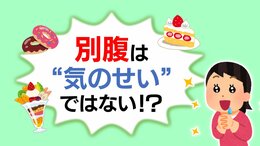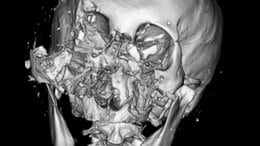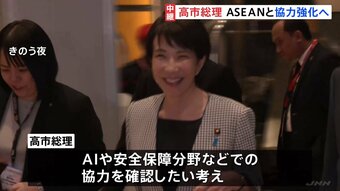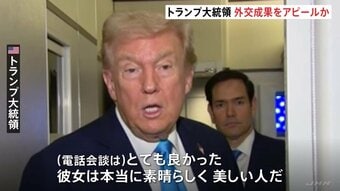減税は本来、有効な政策手段
本コラムでは以前、減税の議論が必要だと書きました。それは、政策手段として、減税が有効なケースもあるからです。
まず、1回限りではなく、賃金が物価に追いつくまでの間、家計支援を複数年、行うのであれば、現金給付よりも減税という制度にした方が理にかなっています。
次に、すでに6兆円も使ったガソリンへの補助金や、電気ガスへの補助金などの出口を考えるのであれば、それら個別補助金を打ち切って、家計支援の減税一本に切り替えたほうが、合理的です。
補助金の長期化は、市場機能を損ない、省エネ工夫にも貢献しません。家計支援を何に優先的に使うかは、本来、家計の選択に委ねるべきなのです。
それを今回は、減税も補助金も両方やるというのですから、整合性もやや欠いています。
さらに言えば、減税には、大きな意味で、政策をめぐるお金の流れを変えるという意味もあります。
コロナ対策以来、企業や業界には次々と補助金が支給され、投資や賃上げのためという名目で政策減税が繰り返されています。
税金を集めて、声の大きなところに分配することを、これ以上、積み重ねるよりも、そもそも集める額を減らして家計支援する方が、スジが通っているという面もあるように思います。
「減税」という形が何より大事?
もっとも岸田総理は、こうした構造的な問題にはあまり関心がなかったようです。
とにかく「減税」の形にして、増税イメージを払拭することが、より大事だったのかもしれません。
補助金や企業向け減税に偏った政策から、直接的な家計支援に踏み切ったことは大きな政策選択です。
そして、数兆円のコストもかかります。にもかかわらず、そうした政治的な動機を見透かされ、前向きに受け止められていないのだとしたら、とても残念なことです。
もしも、岸田総理が2024年以降も、この家計支援を続けるために、今回、敢えて減税の形を選んだのだとしたら、なかなかの「役者」ですが・・・。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)