
富山市で聞くと半数を超える約6割の人が「七越焼き」と回答。その「七越焼き」を製造販売する『七越』。創業1953年、現在は富山市内に4店舗を構え、あんこの他にもカスタードやたまごサンドの具が入った「七たま焼」など時代の流れに合わせバリエーション豊富な「七越焼き」を提供しています。

小西アナ:
「どうして七越焼きっていう名前なんですか」
七越・長谷河宏さん:
「詳しくは僕も分からないんですけど七越の越は、越中の越で。
奇数の縁起のいい数字で、ラッキーセブンみたいな感じで聞きました」
小西アナ:
「県内で七越焼きという名が浸透していることをどう思いますか?」
七越・長谷河宏さん:
「うれしいですね、地域密着というか」
優しい甘さで、ほのかにあたたかい。これからの季節に恋しくなるこのお菓子の呼び方について全国的な調査をした人がいます。奈良大学国文学科の岸江信介教授です。
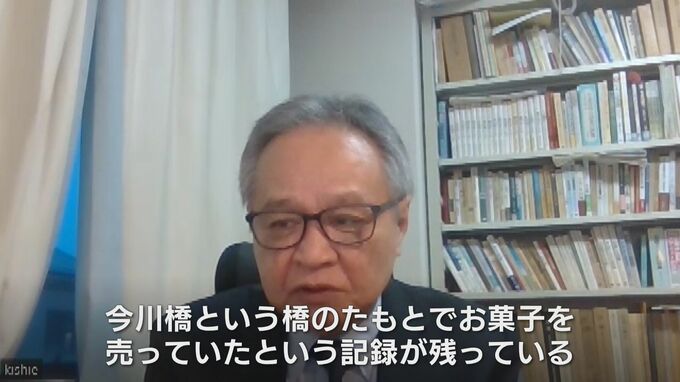
奈良大学・岸江信介教授
「全国各地にいろんな呼び名がある、非常に面白いユニークな存在。年代によっても呼び名が変化する。発祥は東京の江戸。今川橋という橋のたもとでお菓子を売っていたという記録が残っている」

岸江教授によると、このお菓子の発祥は江戸時代初期。当時、江戸の今川橋の横で「今川焼き」が売られていたことがはじまりと考えられています。それから300年たった1950年代。このお菓子にとって歴史的な出来事が起きます。
お菓子とパンの材料や器具・機械の販売を行っている愛媛県松山市の松山丸三が製造機を開発。今川焼きの大量生産が可能になり「大判焼き」と名付け、材料とともに露天商らに販売したのです。

奈良大学・岸江信介教授
「夜店をやる人たちが松山丸三というメーカーの機械を発注して買った。手っ取り早く商売できるということで各地で売れた。きょうはここで盆踊りがあるとか」
できたてほかほかで手にもって気軽に食べられる…。当時の日本人にとっては、まさに新感覚のスイーツだったのかもしれません。全国に一気に広がりました。
奈良大学・岸江信介教授
「地元の会社名をつけるとか屋号、各地で名称をつけた。日本各地に色々な名称が広がった。名称が多様化した。富山市内だったら七越、地元の人がそう呼ぶようになった」














