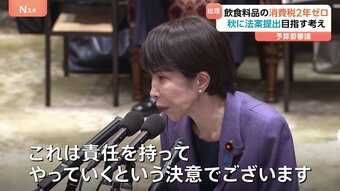改正案提出の意図 条例の実現性は?
改正案が提出された背景には、児童の放置による死亡事案が多発していることがあります。
子どもの放置を巡っては、2023年8月に福岡県北九州市で0歳の男の子が、9月には岡山県津山市で2歳の男の子がいずれも車に置き去りにされて死亡する事件が起きていて、今回、条例改正案を提出した議員団はこうした事件を防ぐ目的があるとしています。
この虐待禁止条例改正案は、10月13日に採決され、可決の見通しだということです。
2024年4月1日の施行を目指しています。
恵俊彰:
子どもたちを守らなきゃいけないということに関しては何の異存もないんですけれども、やはり現実的であるかどうか。例えばごみ出しとか、子どもたちだけで公園で遊ぶとか、この辺りはいかがですか?
前大津市長・弁護士 越直美氏:
やはり現実的ではないですし、県民の方の現状を見ていない。県民の方の声を聞いていないんじゃないかなと思います。今PTAの方も、反対の署名をされています。
今回ポイントなのは、議会が作った条例ということなんです。
普通は県・知事の側が条例を作るときは、やはり普段から県民の方に接しているので、県民の方の現状がわかっています。大津市でも実は市議会が条例を作ったことがあって、その際は議会としてしっかりパブリックコメントとして、市民の方にどうですかと意見を聞いたりしました。そうすると反対意見があって、それを含めて条例を作ると。
さらに、別の懸念もあるといいます。
前大津市長・弁護士 越直美氏:
もう一つこの条例で懸念があるのは、「通報する」ということになっていますので、県とか市にたくさん通報が来ることになります。
今でも児童相談所はすごく深刻な通報が多いです。そういう中で「子どもが1人で帰ってます」という通報が増えると、本当に深刻な事例に対応できなくなる。
ですのでやはり県にも意見を聞かないといけないんですけれども、一応自民党ではパブリックコメントを出したみたいなんですけれども、本当に県民の方の声や実際に運用する県の声をちゃんと聞いているのかなというのも、非常に疑問に思います。
コメンテーター 副島淳:
まさに自分も母子家庭で育ったので、幼少期、それこそ小学校1年生から3年生とかは1人で家で留守番してました。
登下校もしてましたし、それをじゃあ「駄目。あなたのお母さんは虐待してます」って言われたら、多分僕、今ここにいないと思うんですよね。
生活もできてなかったと思うので、本当に街の人の声だったり生活スタイルに寄り添っていないのかなっていう印象があります。
現実は多分不可能だと思いますし、ただこれが可決の見通しということで、埼玉県に住む人がいなくなっちゃうんじゃないのかなと思いますけどね。
弁護士 八代英輝:
子どもの命を守っていこうという、この条例が目的とする意図はわかるんですけれども。
アメリカではこういった法律は多くて、例えばニューヨーク州ですと、自宅に子どもを置いて親が外出しただけで最大懲役1年なんですね。
見つけた人も近所の人も通報しなければいけない通報義務というのがあるんですが、背景が全く違うのはやはり治安状況だと思うんですね。
アメリカは、子どもと手を繋いで歩いて、手を離した瞬間にもう誘拐されてしまうリスクが非常に高いですし、スーパーで牛乳パックを買うと驚くんですけど、そこにみんな子どもの顔が書かれているんです。それは「誘拐された子どもたちを探してます」という写真なんですね。
治安状況が日本とは全く違う中で、アメリカで導入されてるからといってアメリカと同じような条例を直ちに導入すると、社会にそぐわないものになってしまうんじゃないか。
現状、保護責任者遺棄罪等で対応しています。もちろんとんでもない親がいるのは確かなんですけど、現状の社会情勢と合わせてじっくりと考えていくべき問題なんじゃないかなと思いますね。
今週金曜採決 今後は
恵俊彰:
今週の金曜日(13日)に採決があって、可決の見通しだってなると、県民の声が届かないってことになるんでしょうか?
前大津市長・弁護士 越直美氏:
そうですね、本当はもっと前にパブリックコメントをしておかないといけない。
ただ、もしも可決されたときに、知事の方が「再議」という手続きはあります。
まず一般再議というのがあって、内容がおかしいと思えば、もう一度再議というのを議会にかけることができます。再議をすれば、3分の2の賛成が必要です。
ただ、埼玉の県議会の構成を見てみると、自民党・公明党で3分の2あるようですので、再議をかけても可決される可能性があると。
もう一つは、法律違反だというときは知事は再議をかけないといけないというふうになっています。再議をかけてまた可決されたときには、知事は国に対して審判、もう一度審議してくださいと求めたりすることはできます。
恵俊彰:
県民の皆さんがどういう反応をなさるのか。今後どうなっていくんでしょうか。
(ひるおび 2023年10月9日放送より)