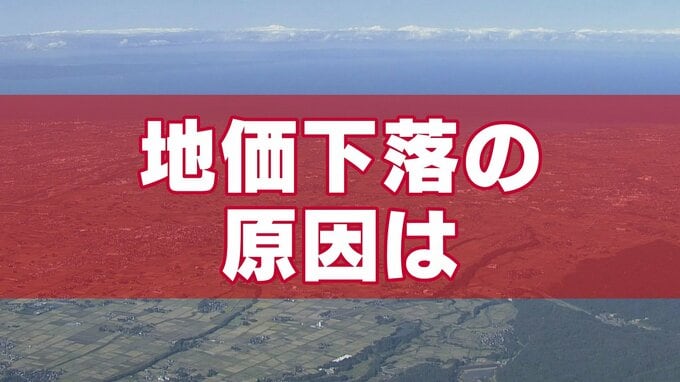富山県内の地価は二極化が進んでいます。土地取引の目安となる地価調査の結果が19日公表され、富山県内全体として地価の上昇地点は増えていますがそのほとんどを富山市が占め地価の二極化が進んでいることがわかりました。不動産鑑定士は「新しく外から入りにくいような町」が下落を招くと指摘しています。一方、農村集落の地域で26年ぶりの上昇となった自治体も。そのワケとはー。

地価調査は土地の取引価格の基準にするため、富山県が毎年7月1日時点の価格を調べ9月下旬に公表しています。その結果、地価の変動率は県内平均で0.1%の下落と前の年よりも下落率は縮小したものの31年連続のマイナスとなりました。
調査では県内の住宅地や商業地など226地点を対象に調べ、上昇したのは60地点下落は95地点でそのほかは横ばいとなりました。その具体的な傾向について専門家は…。

不動産鑑定士 竹田達矢さん:「商業地は特に、昨年0.1%から0.4%に上がっています。この上がり分はだいたい富山市の駅周辺の整備にともなう地価上昇ですね。これが引っ張っているような形です」
富山県内全体としては、地価の上昇地点は増えていますが、そのほとんどを富山市が占めています。
加賀谷悠羽記者:「県内で最も地価が上昇したのは富山駅北側の富山市牛島町です。コロナ禍が明け、商業地としての機運もますます高まっています」

富山市牛島町の地価は38万5000円で前の年より6.9%上がりました。富山駅北側エリアは中規模ホールが開業さらに複合ビルの建設や北陸銀行本部の移転などが決まっています。また、新型コロナの5類移行で人の往来が増加し商業地として期待されるほか、住宅地としての人気も根強く地価の上昇傾向は強まっているといいます。