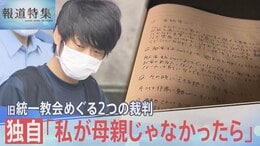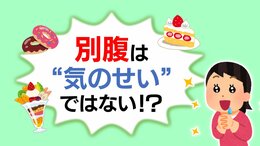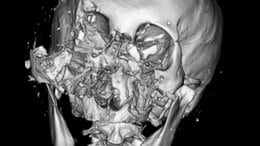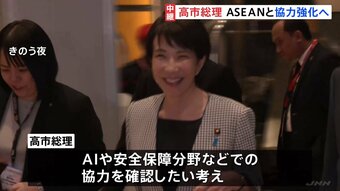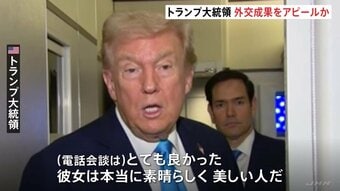物価上振れと円安が背中を押す
では、どういった状況変化が、植田総裁を「発信」にまで踏み込ませたのでしょうか。
1つは物価の上振れであり、もう1つは円安の進行でしょう。
日銀は7月に、今後の消費者物価の見通しを上方修正しました。2023年度は2.5%と見通しを引き上げましたが、逆に2024年度は1.9%と再び2%割れに戻るという予想でした。
しかし、その後も3%台の高い物価上昇が続き、サービス価格にまで上昇の波は広がっています。
さらに原油価格が再び高騰し、ガソリンや電気代などへの波及が避けられないことから、物価の更なる上振れは確実との見方が大勢です。
2022年度も含め、3年続けて2%以上であれば、「デフレ脱却」と言っても、誰も文句は言わないでしょう。
円安の進行も誤算でした。
7月の長期金利の変動幅修正によって、いったんは1ドル=138円台まで円高に戻したものの、その後は、アメリカのインフレの粘着性に焦点が移り、日米金利差が意識されたことから、147円台まで円安が進行してしまいました。
2022年、市場介入した際の145円を超える円安は、物価高対策を迫られている日本経済には、明らかに好ましくないと、植田総裁は思っていることでしょう。
アベノミクス終了を政治的に受け入れられるか
植田総裁の発言は、素直に読めば、年末まで、物価、賃金、経済対策や来年度予算など政府の政策も見た上で、早ければ2024年1月に物価見通しを修正すると共に、マイナス金利を解除する、というシナリオです。
年初が早過ぎるならば、春闘の結果がはっきりする春には解除、というシナリオも選択肢でしょう。
その頃までに、自民党内のリフレ派、アベノミクス信奉議員らが、緩和修正に納得できる状態になっているか、という政治的な環境も、政策転換を決める、意外に大きな要素になると見ています。
一方、テクニカル的には、長期金利の変動幅を1.0%以下にするという今のYCC(イールドカーブコントロール)を、いつ、どのように変更するのかも、大きな課題です。
短期金利がマイナスからゼロになれば、イールドカーブも上にシフトしてしまうからです。
YCCの更なる変更や撤廃が先にあるのか、それとも、マイナス金利解除と同時決着になるのか、注目されます。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)