なり手不足の解消へ 目指すのは『潜在的な教員』の掘り起こし
では、臨時教員を採用すれば問題は解決するのでは?とも思えますが、それも簡単なことではありません。
教員を希望する人材の大半は、すでに新年度の時点で採用されていて、毎年2000人あまりが臨時教員として、すでに教鞭をとっています。このため次の方策として教職の志望順位の低い人たちの中から意欲のある人材を確保することになりますが、厳しい人材獲得競争の中ではそう簡単ではありません。
学校人事課・稲福政彦班長
「ぜひ、みなさんのお力が必要です」
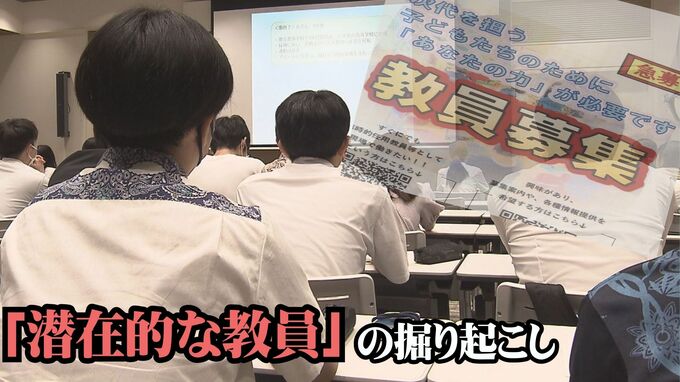
この現状を解消するために県が今年から力を入れているのが、教員免許を持ちながら教員にならずに就職したり、子育てを機に学校を離れたりした『潜在的な教員』の掘り起こしです。
ことしに入って複数回、説明会を開催したり、実際の授業の見学や現役教員との意見交換などの場を設けたりして、人材に対して『教員の仕事の見える化』に取り組んでいます。求職者からのアプローチを待つのではなく、興味を持ってもらいやすい環境を作るのが狙いです。
このほか、採用の年齢制限の引き上げや、臨時教員として3年以上勤務した場合に正採用試験を一部免除するなど特別枠を設けたほか、各学校や各地の教育事務所も採用活動を行うことで、少しずつ成果が出てきています。
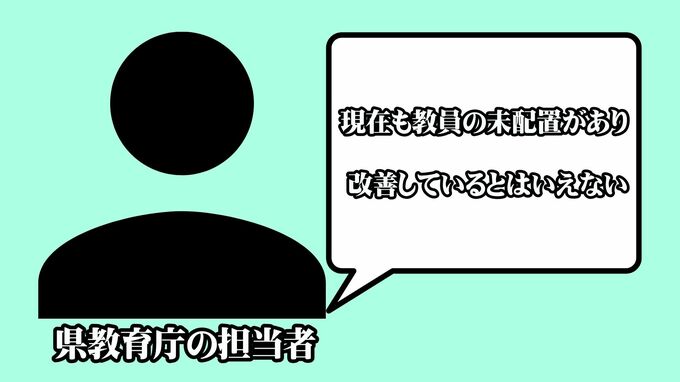
しかし県の担当者は「若干回復しているかもしれないが、現在も教員の未配置があり、改善しているとはいえない」として、更に取り組みを進めたいとしています。
子どもたちの学びの環境を整備するとともに教員の働き方を改善するため、教員不足問題の解消に向けた取り組みをさらに進めることが求められています。










