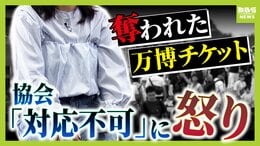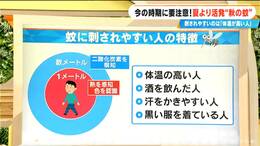自動車に相乗りできる「ライドシェア」。日本では原則禁止ですが、タクシー運転手の減少問題の解決策の一案として政治、経済界から注目を集めています。
ライドシェアをめぐる日本の動き、そしてリスクやメリットについて詳しくみていきます。
運転手は減少も、訪日外国人は増加
南波雅俊キャスター:
ライドシェアとは、自動車の相乗りです。タクシーではなくて、自家用車の空いた座席を活用していくというわけです。
タクシーの運転者数は減ってきています。2019年度、コロナ禍前と比べると、4万人ほど減ってます。その一方で、訪日外国人の旅行者は、コロナ禍の2021年には25万人ほどだったのが、2022年には383万人ほど。2023年は、半年で1300万人を超えてますので、一気に戻ってきているという現状があります。
こうした現状の中で、菅前総理は、「(タクシーについて)現実問題として足りない。そうした方向(ライドシェア解禁)も必要かなと思ってます」とコメントしたわけです。

例えば、2023年の夏、京都などではタクシーが足りなくて、一般の皆さんが乗れないというようなニュースもありました。
ライドシェアの仕組みですけれども、目的地を一緒とする人が、相乗りで目的地に向かっていくというもの。海外では、2010年代には70か国以上にあって、ビジネスとしての普及も行われています。ただ日本では、営業許可のない“白タク”というのは、法律上、道路運送法で原則禁止されているという実情があります。

そんな中、JNNが世論調査を行ったところ、ライドシェアの導入に反対という意見が55%と半数超えているわけなんです。

若新雄純・慶応大学特任准教授:
アンケートで、導入に賛成か反対かを聞くのは不思議な話だと思っていて。世の中のタクシーを、すべてを相乗りにしますって話だったら、反対っていうのはわかるんですけど、これは選択肢を増やす話なんですよね。つまり、自分は今まで通りのタクシーがいいって思ったらタクシーを選べばいいし、相乗りでもいいよ、その方が便利だよって人は、ライドシェアを選べるようになる。
質問は、賛否よりも、好きか嫌いかで聞くべきだったと思う。新しい選択肢を提供するだけの話なのに、その選択肢に対して、すべての人が合意しないと始まらないっていう問いかけは、ちょっとしんどいなと思う。このスタイルが好みではないって人が多いんでしょうね。