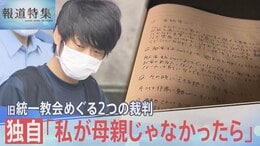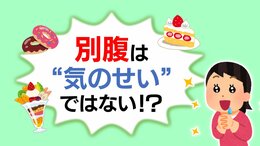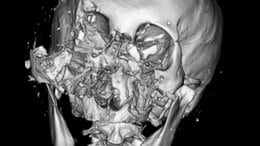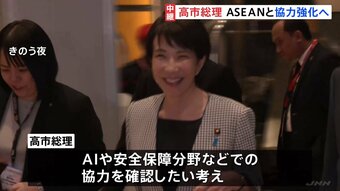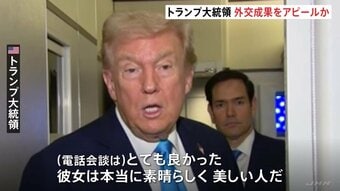賃金が上がらなければ、インフレ課税に
一方で補助金効果のあるエネルギーを除くと、物価上昇の勢いは衰えていません。8月の生鮮食品とエネルギーを除いた、いわゆるコアコア指数は、前年同月比4.0%の上昇で、7月と同じ上昇率でした。この数字こそがインフレの基調です。
「物価と賃金の好循環」が目標とは言うものの、現実には、賃金上昇は物価に追いついておらず、実質賃金は15か月連続でマイナスです。
個々の家計の消費行動に関わらず、所得が減っているのですから、知らない間に増税されたのも同然です。今、起きていることは、「インフレ課税」と呼べる状況です。
とりわけ、今の物価上昇が、当初の戦争による輸入価格の上昇だけでなく、異常なまでの円安によって一段と加速されていることを考えると、インフレ課税は家計に最も厳しく表れていると言って良いでしょう。
その逆に、企業には名目売上高の増加、とりわけ輸出企業には円安による利益底上げという「ボーナス」がもたらされています。
一番、恩恵を受けているのは、財政=政府の税収でしょう。名目物価の上昇で消費税は自動的に増収になります。企業からの法人税収も増えています。
所得税は累進課税なので、賃上げで名目賃金が上がれば、賃金上昇を上回る税収があがります。
要は、インフレ課税を通じて、家計から企業や国の財政に、強制的な所得移転が行われていると言うこともできるのです。
物価を目標の2%に抑制し、賃金上昇を
そのインフレ課税をいくばくか緩和するために、食料やエネルギーに対する補助を、増えた税収から財政出動することは、やり方にはいろいろ工夫が必要にせよ、理にかなっているように思います。
2023年の春闘では30年ぶりの賃上げが実現しました。それでもベースアップはせいぜい2%です。
「物価と賃金の好循環」の実現を目指すのであれば、インフレ課税が行き過ぎないように、2%を超えるようなインフレを抑えること、そして同時に、来春以降も継続的な賃上げを実現すること、その両面作戦が必要に思えます。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)