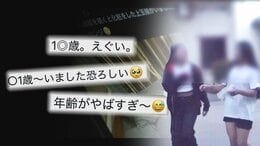■徐々に“元の生活”へ メリハリのある感染対策を
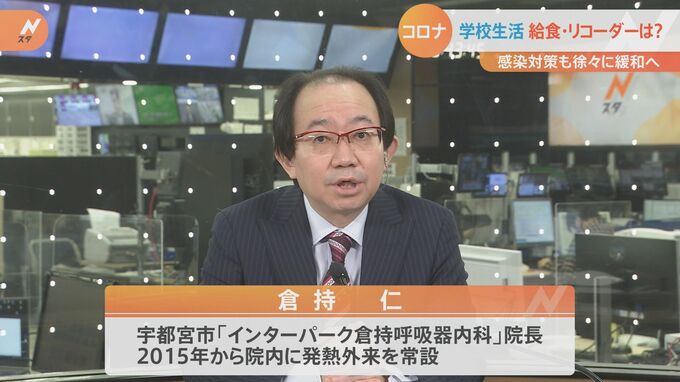
ホラン千秋キャスター:
様々なところで、感染対策をしっかりと適切にしながらも、元の生活に戻ろうとする動きというのはいろんなところで見られますね。
インターパーク倉持呼吸器内科 倉持仁 院長:
今のように感染が減少している時期には、こういった動きが見られるのは普通ですし、ただし次にまた増加に転じた場合に速やかにその感染状況を把握できるような検査体制やあるいは、例えばハンドドライヤーなどは、本質的な問題はきちんと空間が喚起されているか否かという点に尽きますので、やはりそういったところを見直すということが大事になってくると思います。
ホランキャスター:
倉持さんは検査体制について以前からお話されていますけれども、具体的にどのように整えておくことが適切だとお考えなのでしょうか?
倉持医師:
特に感染流行期に感度が高いPCR検査をきちんとできるようにしておく。流行期になってしまうと感度の悪い抗原検査も利用しても足りないというような状況が今まであったわけですから、そういったことをコロナの株に合わせて複数回できる体制っていうのを今作っておくべきだと思います。
井上貴博キャスター:
倉持先生ご自身はお子さんいらっしゃいますけど、こういう環境だとマスク取っていいよというのはどういう環境で伝えていらっしゃいますか?
倉持医師:
やはり家族で過ごすときや家族内で車で移動するとかそういったとき、あるいは外を散歩したり、周りに人がいなければ付けていません。逆に学校などで様子を見せていただきますと、各お子さんしっかりマスクをつけてメリハリが効いていますので、やはりその辺もしっかり大人が適宜間違ってる場合には指摘をしてあげればいいんだと思います。
井上キャスター:
熱中症のリスクとのバランスはどうですか?
倉持医師:
熱中症も暑い中での集団での運動などで起こってきますから、学校単位で運動する管理者は、きちんと温度管理をした上でどのぐらいの時間運動させるとか、そういう指示を出す必要があると思います。マスクだけの問題ではないと思うのです。
井上キャスター:
温度管理というのは?
倉持医師:
例えば、気温が何度まで上がるかというのを把握した上で、運動のメニューを決めていくということをしないことが多いので、最近の熱中症というのは集団でたくさん出てしまうことが多いんです。ですからそういう管理が必要ということです。