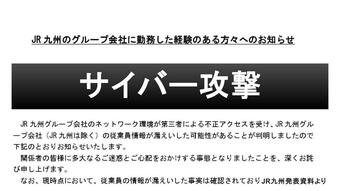■もし帰宅困難者になったら…受け入れ施設を把握する
東日本大震災の時には、公共交通機関がストップし、渋谷駅などが大勢の人であふれました。このようなことにならないためにはどうしたらいいのでしょうか。
帰宅できない人たちを当時救ったのは、学校や商業施設などが一時受け入れ施設として開放されたことでした。一時受け入れ施設のひとつ、東京都中央区の築地本願寺に聞きました。

ーー災害時などには何人ぐらいの受け入れが可能ですか?
築地本願寺 東森尚人(ひがしもり しょうにん)副宗務長:
屋内に3つの広間を用意しておりまして、361人の一般の帰宅困難者に開放させていただく予定になっています。
ーー備蓄品の量はどれ位ありますか?
東森副宗務長:
361人の方が3日間お過ごしいただく部分は最低限保存しているのと、それ以上の量の水を用意をさせていただいております。
保存食として、チキンライスや五目ご飯。その他にもアルミのブランケットや簡易トイレなど、お水以外にも様々なものが用意されています。
ーーいつから避難者を受け入れていますか?
東森副宗務長:
もう100年前になりますけれども、関東大震災の折にも救護所を設けたり、様々な救援活動をしておりました。本堂も元々は木造だったんですけれども、関東大震災で焼け落ちてしまいましたので、復興の際、揺れに強く火災に強いということでコンクリート製になっております。

ーー東日本大震災のときも受け入れをされましたよね。
東森副宗務長:
約500人の方々に泊まっていただきまして、僧侶、スタッフでおにぎりやスープなどの炊き出しを行ったり、トイレなど貸し出しをさせていただきました。
ーー対応される職員やスタッフの方は何人かいらっしゃるんですか?
東森副宗務長:
総勢150名程の職員がおりまして、緊急連絡網や災害時の対応マニュアルを備えております。最近の言葉でBCP(事業継続計画)として、災害に遭ったときにどう事業を正常に戻していくのかといった計画を立てたりとか、そんなこともしております。
災害はいつ起こるかわかりませんし、築地本願寺も災害に遭ってきた歴史もございますので、より一層、防災減災に力を注いでいきたいと思います。
恵俊彰:
色んなシナリオ、自分だったらいつも勤めてる会社はここだ、そこから家に帰る方向は東西、その途中にはこんな帰宅困難者を保護してくれる施設があるとか、そういうことを分かっておくだけでも、歩いてみるだけでも、ひょっとしたら違うのかもしれないですね。
アートプロデューサー 栗栖良依:
私はフリーランスで、毎日違う場所に出没するので、本願寺のような誰でも受け入れてくれる場所があるということを知っているだけですごく安心できる。
恵俊彰:
基本的には、どこでも、誰でも受け入れてくれるんですよね。どこの区に住んでいるとか関係ないんですよね?
山村氏:
そうです。避難所ポータルサイトもあります。
駅とか大型施設の場合、一時滞在施設を準備しています。情報はネットで見られるので、自分のいる場所に近いところを選んでいくといいと思います。企業が地域と連携して進めていくということで、六本木ヒルズや渋谷ヒカリエなど、各商業施設でも受け入れてくれるのは有難いなと思いますね。
また、東京都では「帰宅困難者条例」というのがあって、各事業所で極力「一斉帰宅抑制」を図って、3日間ぐらいは学校や会社で保護してもらうんです。
帰宅困難者に関するシナリオには
▼街に人があふれることで、負傷者などの救出・救助活動への支障になってしまう
▼帰ろうとする途中で余震などに遭い、火災に巻き込まれたり怪我をすることもある
とあり、無理に移動しないということも大事です。
ーーどのぐらいの期間、移動せずにいればいいのでしょうか?
山村氏:
安全な一時受け入れ施設に移動した場合には、公共交通機関が復旧するまでは待機した方がいい、これが一つの目安。徒歩で帰宅できる距離であれば、安全が確認できた時点で帰宅してもいいと思います。
少し遠い場合は、特に直下地震の場合、余震が頻発して壊れかけた建物が倒れたりする危険性がありますので、二次災害に巻き込まれないようにすることが大事だと思います。そのために安全な場所で様子を見てください。