「もう絶句」いじめは無かったことに…主観的な受け止めと切り捨て

迎えた5月26日の判決。大阪高裁の冨田一彦裁判長は、女子生徒が受けた仲間外れについて「女子生徒が自然とグループから離れていった可能性もあり、仲間外しと捉えるかは主観的な受け止めの問題」といじめを認定しなかった。
また、学校が実施した心理テストで女子生徒が「死んでしまいたい」「遠くへ行ってしまいたい」という項目に「かなりあり」と回答していたものの、総合評価で「深刻な挫折をもたらすような情況の急変がなければ、具体的問題へと発展する可能性はあまりない」とされた点を捉え、「学校の教職員が自死の危険性を認識するのは困難だった」とした。
第三者委員会がいじめと認定している点については、「訴訟の相手方の反証・反論を踏まえて判断すれば、必ずしも第三者委員会と同一の結論に至るとは限らない」として、第三者委員会の調査報告に沿った判断はしなかった。さらに、学校が女子生徒死亡後に行った無記名アンケートも「女子生徒の自死という事実を知ったうえで、自死に影響し得た他の要因に対する十分な情報を与えられたとは限らない状況の下でされていて、信用性の評価は慎重にすべき」と、判決の判断材料に採用しなかった。
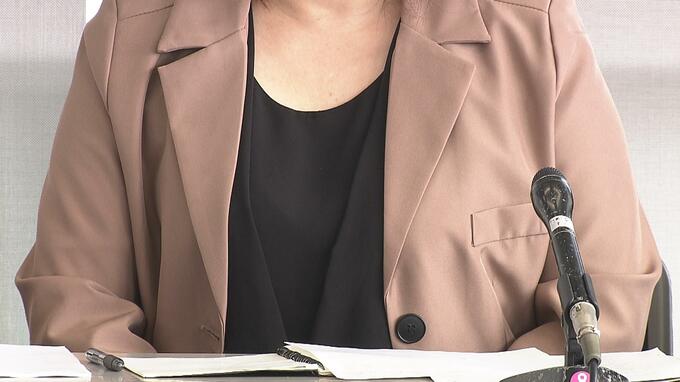
(女子生徒の母親)「亡くなった娘の『気のせい」で特にいじめは無かったという風な判断をされているということ、もう絶句でしかないです」
弁護団からも、憤りの声が相次いだ。
(藤澤頼人弁護士)「調査委員会の調査を中心に我々は立証していくし、報告書で足りないなら調査の方法を委員長に聞いてください、あるいは原本・調査記録を出してくださいと話していたのに全て排斥して、そのうえで主張立証できてないんだと。結論ありきというか、こういう風に誘導した裁判ですか」
(石田達也弁護士)「学校が子どもたちの自死という問題について、最後のゲートキーパーということを完全に無視した、見殺しにしていいですという判断。」
第三者委員会での関係者証言やアンケートは、比較的記憶も鮮明なはずなのに裁判では一顧だにされない。そして、被害を証明する責任を負う被害者側が必要な証拠は、相手方の自治体次第で手に入るか分からない。「司法」という最後の砦は、いじめ被害者にとってはあまりにも高い壁として立ちはだかっている。














