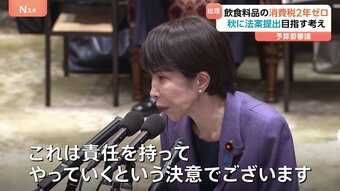中国25.6%、ノルウェー79.3%、ドイツ15.7%・・・日本1.7%。これは去年の自動車新車販売台数の内EV(電気自動車)の割合だ。百年に一度と言われる自動車産業の変革期。去年ついに世界のEV販売台数が1000万台を超えた。しかしそのうち6割近い590万台が中国だ。なぜ中国はこれほどまでにEVが普及したのか…。一方、日本はなぜEVの波に乗り遅れているのか議論した。

「あっと口を開けて見ている間にシェア25%になってしまった…。業界全体戸惑っている」
中国の都市部を見るといたるところでEVが目に付く。タクシーは殆どがEVだ。EVと言えば普及を声高に叫んだのはヨーロッパで、実際にEVを普及させたのは世界最大のEVメーカー『テスラ』を有するアメリカだ。ところがこの数年で中国が突然EV界のリーダーになってしまった。一体どんな経緯だったのか、専門家に聞いた。

自動車アナリスト 中西孝樹氏
「2019年には新エネルギー車ってEVもプラグインも売れなかったんです。補助金いっぱいつけてもダメで…。なので我々も正直言って油断してたんですが、2020年にホンガン・ミニ(45万円で売り出した『宏光MINI EV』)というとても安い車がバカ売れした。そして、『テスラ』の上海工場ができて大きな刺激になって、高級車のセグメントで色んなブランドがEVを出した。つまり安い車と高い車でまずEVが売れるようになった。でも日本車が位置する真ん中の15万元から25万元、200万円から400万円の所でEVは売れてなかった。それを変えたのが『BYD』でして、コストの安い、しかし質も悪くないEVを出してきて、真ん中のクラスで売れ始めた。これが2021~2年のことで…。あっと口を開けて見ている間にシェア25%になってしまった…。業界全体戸惑っている状態です」
『BYD』は中国のバッテリーメーカーだったが、現在中国国内では『テスラ』を抜いて販売シェアトップのEVメーカーとなった。 今年日本にも上陸。400万円台で、航続距離400キロを謳い、日本のメーカーの脅威となっている。
日本でもEVは近い将来大きなシェアを持つだろうが、まだ何年か猶予があるだろう、それまでに色々と対策を…、考えていた。確かにEVシェア1%台の日本では急激な成長は考えにくいが、経済評論家の加谷珪一氏は“工業製品のS字理論”を語る。

経済評論家 加谷珪一氏
「歴史をさかのぼると、白物家電しかり新しい工業製品が出て、普及率が2割近くなると爆発的に普及する。あらゆる工業製品に言えるんです。(中略)中国はかなり先行しているが、世界で販売台数の2割近くになると、(それまでゆっくり伸びていたものが)突然一気に普及するんです。・・・どっかのポイントでS字型に急成長する。工業製品はみな同じなんです」
つまり日本は1割すらほど遠いが、世界シェアが2割に近づくと急激にEVシェアが伸びる。その時日本だけが取り残される可能性があるということか…。