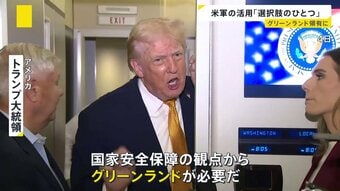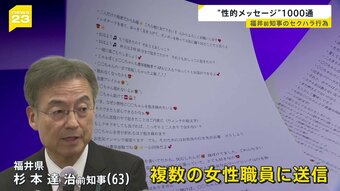4.ウクライナから避難した人たちは救われるのか?
改正案は「難民には当たらない紛争避難民など、人道上保護すべき人を確実に保護するため」として「補完的保護対象者認定制度」の創設をうたう。しかし、ここにも矛盾がある。
難民とは、人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員、政治的意見という5つの原因のいずれかによって、迫害を受けるおそれがあるため、母国の外にいる人を言う。
「補完的保護対象者認定制度」は、5つの原因には当たらなくても「迫害を受けるおそれ」のある人たちを対象に“準難民”として保護するのだという。
だが、全難連代表の渡辺弁護士は、「これまで入管庁が多くの事例で難民と認めてこなかったのは、迫害や迫害の恐れを国際基準より狭く解釈してきたからだ。5つの原因に当たるかどうかではない。迫害する側から個別に把握されなければ難民認定しないという独自の基準を変えない以上、保護が拡大するとは思えない。しかもウクライナの人たちの保護は、査証の発給から始まっているので次元が違う」と指摘し、新制度は、EUが共通ルールとしている「補完的保護制度」などと似て非なるものだと強調する。
全難連は、入管庁が17年からの5年間で紛争からの退避を理由に人道配慮で在留特別許可を認めた14件を分析、12件は「補完的保護対象者」には当たらないとしている。
しかも、いまの難民認定と手続きも、担当者も同じだ。昨年は、難民の“一次審査”だけで結論が出るまでに平均2年9カ月がかかっている。迅速な保護はあり得ない。
そもそもUNHCRの「国際的保護に関するガイドライン」では、戦争避難者も難民と認定され得る。人道配慮による在留特別許可も含めれば、いまの法律で対処は可能だ。現にウクライナからの避難者は新制度を待つまでもなく手厚く保護されているし、アフガニスタンの人たちも難民と認定された。
「入管庁は改正案全体を通すために、戦争から避難したウクライナの人たちを口実にしている。火事場泥棒だ」。厳しく批判されるゆえんは、ここにある。
5.原則収容主義からの転換になるのか?
収容に代わる「監理措置」は、退去強制令書が発付された人に対して主任審査官が、逃亡の恐れや収容によって受ける不利益、その他の事情を考慮して収容するか、「監理措置」かを判断するという。
「監理措置」となれば「監理人」の下で社会に出て生活する。2年前の法案は、「監理人」に生活状況の報告義務を課し反発を呼んだが、今回は、必要があるときに報告を求めると修正された。収容された場合は3カ月ごとに見直すかどうか検討するという。
2年前の国会で参考人を務めた児玉晃一弁護士は「“その他の事情”であれば何でもありだし、『監理人』の報告が必要と決めるのも主任審査官の裁量だ。報告が必要とされれば、民間人に動静監視を義務付けることになる。就労や逃亡には懲役も含む刑罰が設けられるので、いまの『仮放免』より強固な締め付けになる。入管庁に都合がいいだけだ」と批判する。
現在の「仮放免」では、本人と信頼関係のある弁護士や支援者が保証人になっている。多くは「監視義務が生じる『監理人』は引き受けない」と言う。成り手がいなければ、金銭で請け負う“監理人ビジネス”の余地が生じる。人権侵害の温床となった“生活保護ビジネス”の二の舞にさえなりかねない。
6.改正案で問題は解決するのか?
入管施設ではこれまで多くの命が失われてきた。入管当局に対する不信は非常に強い。にもかかわらず難民審査、収容、仮放免、退去強制、在留特別許可…と、いずれも重要な判断が、裁判所の関与なく入管庁の裁量に委ねられている。改正案は、その権限をさらに広げようとしているのではないか。
難民審査参与員でもある鈴木江理子・国士舘大教授(社会学)は、「裁量によって他人の人生を左右するのはあってはならないこと」としたうえで「入管庁は、管理監視強化によって排除を推し進めているが、求められるのは、適切な難民保護と人道的な視点からの在留特別許可、そして送還を拒む人を新たに生み出さないための移民・難民政策の確立、それに向けた法整備だ」と語る。
一連の取材で聞いた阿部教授の言葉をあらためてかみしめている。
「国境を管理する入管庁が難民認定に関わる仕組みに極めて問題がある。入管庁とは切り離し、国際的な人権基準を守り、難民保護を目的とした独立機関を設けない限り、根本的な解決にはならない」
「現行入管法の課題」はここに尽きる。