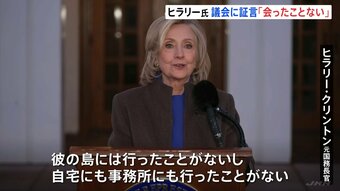古来「戦争は始めるよりも終わらせる方がはるかに難しい」と言われる。“プーチンの戦争”といわれる今回のウクライナ侵攻。ロシア側の思惑通りには進んでいない中、プーチン氏本人も振り上げた拳の下しどころを苦慮しているのではないだろうか?番組では、歴史を振り返りながら“戦争の終わらせ方”を議論した。
■「第二次世界大戦で、対ドイツと対日本では“終わらせ方”が違った」
戦後日本では戦争を放棄したことで、いかに戦争をしないかは研究されてきたが、始まってしまった戦争をいかに終わらせるかには関心が持たれてこなかった、と話すのは防衛研究所の千々和泰明主任研究官だ。千々和氏は戦争の終わらせ方を研究し大きく2つに分類した。即ち…
①将来の危険を排除する紛争の『根本的解決』
②交戦相手の条件を考慮する『妥協的和平』
前者では、相手が“存在すること”による危険性を重視し、それを取り除くため、ある程度の犠牲を払ってでも徹底的に打倒、駆逐する。
後者は、将来的危険性よりも、現在の味方側の犠牲をこれ以上増やさないことを目的としたものだ。
例えば①の『根本的解決』の典型となるのが第二次世界大戦の対ドイツとの戦争の終わらせ方だ。
防衛研究所戦史研究センター 千々和泰明 主任研究官
「ナチスはヨーロッパを支配し、ユダヤ人を虐殺、ロシアへの人種戦争を仕掛けていった。このような危険な体制を妥協して講和してしまえば、将来もう一度ナチズムと戦わねばならない。だから今徹底的に叩いてしまわなければならない。ということでベルリンまで侵攻して、ヒトラーを自殺に追い込み、ドイツという主権国家そのものを消滅させた。戦争末期には親衛隊のトップだったハインリヒ・ヒムラ―などナチス幹部は和平を求めましたが、連合国は頑として応じなかった」
連合国側はこの戦争で約1170万人の犠牲者を出した。もっと早く何らかの有利な条件のもと和平に持ち込めば犠牲は少なかっただろうが、それよりもヒトラーやヒトラー的なものが生き残る未来を封じる選択をしたのだ。アメリカ・ルーズベルト大統領はナチスが存続して和平が成立した場合の将来についてこう語った。
「人類に何が起こるか考えると私は身震いする」
一方、ドイツと同じ枢軸国だった日本に対して、連合国は対ドイツとは違う終わらせ方を選んでいる。日本における第二次大戦とは太平洋戦争に他ならず、連合国とはほぼアメリカといってよい。
ルーズベルトの突然の死によって就任したトルーマン大統領は「日本が無条件降伏するまで攻撃を続ける」と声明を出した。アメリカはソ連の参戦を知っていた上で、本土決戦、核使用ともに準備を進めていた。つまり対ドイツと同様の終わらせ方も可能だったのである。だが、アメリカの“終わらせ方”は違った。ドイツと日本、どこで道が分かれたのだろうか?
防衛研究所戦史研究センター 千々和泰明主任研究官
「一つは日本の軍国主義も真珠湾攻撃など色々しましたが、やはりナチズムとは違うんじゃないか…。ナチズムのような民族虐殺とか人種戦争はしていない。(中略)もう一つは、犠牲です。本土決戦を考えるとアメリカ軍の犠牲がかなり大きい。ドイツでは本土決戦をやった。相当な血が流れるのを実際に見てきた。日本に厳密に無条件を適用して犠牲が大きくなることは避けるべきという声が国務省や陸軍省からも出てきた。ということでポツダム宣言になるわけです。(中略)大変厳しい条件でしたが、天皇制の廃止がなかった。占領もやがて平和的かつ責任ある政府が樹立されれば連合国は撤退するとか、世界貿易関係に復帰することができるとか…、無条件といいながら条件を出した。これは対ドイツにはなかった」
将来への危機管理を徹底したうえで、犠牲の拡大を回避するという2つの分類でいえば、日本の“戦後”は『根本的解決』と『妥協的和平』の中間点といえる落としどころから生まれたものだったというのだ。
■「妥協的和平の結果が、北朝鮮による核の脅威だ」
続いて②の『妥協的和平』によって休戦に至ったものの一つは朝鮮戦争だった。1950年、アメリカが支援する韓国とソ連、中国が後押しする北朝鮮の間で起きた戦争だ。この時韓国を支援したのは西側16か国で編成された国連軍となっているが9割以上は米軍だった。3年の戦いで国連軍の戦死者は約15万人に上った。
防衛研究所戦史研究センター 千々和泰明主任研究官
「この戦争は韓国が大きく北進したり、北朝鮮が大きく南下したり、2転3転した。北側が38度線を超えて南に押し込んで来たとき、国連軍司令官だったマッカーサーが核兵器を使ってでも戦う、勝利しかないと言った。そんなことをすれば(北を支援する中国やソ連と)全面戦争になってしまうと、トルーマン大統領はマッカーサーを解任する。結局この2転3転する戦争でアメリカ・国連側も中国・北朝鮮、共産側もお互い敵を打倒することは不可能だ、やろうとすれば、もの凄い犠牲が出る、ということで休戦協定という妥協に至った」
犠牲を回避したこの“終わらせ方”の結果、どうなったかというと、北朝鮮が40~50の核を持つという“将来の危険”がいま現実のものとなっているのだ。紛争の解決策は核の有る無しで全く違うと元防衛大臣の森本敏氏は言う。
森本敏 元防衛大臣
「冷戦後の紛争は性格が違う。一番重要なところは核を使えるかどうかになった。なんでイラクのフセインは殺され、ビン・ラディンが殺され、色々な指導者が西側同盟、アメリカによって抹殺されたかといったら核を持っていなかったから・・・。今核兵器を持っている国の人口は世界の半分ある。北朝鮮がもし核を持っていなかったら今存在しないですよ。つまり核を持てば生き残れるんだっていう考えです」
では、今現在起きている戦争、ウクライナに攻め込んだロシアには、誰が選ぶのかは別にして、いかなる“終わらせ方”が選択されるのだろうか?
■武田信玄の言葉…「勝敗は六分か七分勝てばいい」
ロシアの対ウクライナの終わらせ方を先述の2つのタイプに分けると、
『根本的解決』はロシアから見れば、ゼレンスキー政権を打倒し完全属国化することだろう。西側からすれば、二度とウクライナに攻め込まないようなプーチン政権の終焉なのかもしれない。
『妥協的和平』は交渉でお互いに譲り合うこと…ウクライナ側からいえば、せめてロシアが侵攻した2月24日に戻ることであるし、もっと言えば、クリミアを返還したうえで、自治権など特別な権利を与えることだろう。
防衛研究所戦史研究センター 千々和泰明主任研究官
「プーチン大統領が『すいませんでした』といって荷物をまとめてウクライナから出ていくってことにはならないだろうと…。ロシアは権威主義体制の国ですから国家の名誉がかかったことに関して『やってみたら大失敗でした』と国民に言えるか…それを言えばプーチン自身の権力基盤が崩れる恐れがある。現時点では妥協的和平、ウクライナから完全撤退は難しいんじゃないかと思います」
確かにプーチン氏は犠牲を恐れて妥協するくらいなら核を使う道を選ぶかもしれない。
番組のニュース解説、堤伸輔氏も、根本的解決を探ると核を使うか否かということに行きついてしまうとして、過去の取材の時に聞いたこんな話をしてくれた・・・。
国際情報誌『フォーサイト』元編集長 堤伸輔氏
「1991年の湾岸戦争の時、アメリカはあっという間に戦争を終わらせて、イラクを完膚無きまでに叩くことをやろうと思えばできた。でもやらなかった。その時、岡崎久彦さん(元外交官・サウジアラビア大使などを歴任)という保守派の論客が、武田信玄という武将の言葉を引用して私にこうおっしゃた『戦というのは(10が完全勝利だとして)六分か七分の勝利がいいんだ』と。岡崎さんはどちらかというと根本的解決を求めそうな方なんですが、その岡崎さんがそう言ったことに含蓄があって面白かった。だから妥協的和平も妥協の仕方にポイントがあるんだろう」
さて、プーチン氏と今の西側諸国の辞書に“妥協”や“六分か七分の勝利”といった言葉はあるのだろうか?
(BS-TBS 『報道1930』 5月3日放送より)