木の香り漂うぬくもりあるしつらえ。キッチンやお風呂も…。まるでホテルの客室のようですが、実は…。
災害が起きたときの「仮設住宅」です。しかも、トレーラーに積んで容易に移動できるようにつくられているため、「ムービングハウス」=「動く仮設住宅」と呼ばれています。
四国の高知県です。今後30年以内に高い確率で発生すると予想されている「南海トラフ巨大地震」などの大規模な災害が起きたとき、被災者の住まいの確保が課題となっています。高知県は3年前、「ムービングハウス」のメーカーらで作る団体と防災協定を締結。2022年から県内に「動く仮設住宅」を備蓄する拠点の整備が始まりました。
高知県住宅課 大原勝一 課長
「完成品が備蓄できることが大きな利点だと思っています。トレーラーですぐに被災地に仮設住宅を供給できるというのが大きな利点だろうと」
拠点作りを手がけるのは、北海道の住宅メーカー「アーキビジョン21」です。
アーキビジョン21 石塚善光 製造部長
「広さはだいたい30平米ほどあります。非常に断熱性能が高く、北海道でも使ってもらって、外でマイナス20℃、30℃になろうが中で快適に暮らしていただける」
窓ガラスは、北国仕様の3重ガラス。ライフラインさえ復旧すれば、すぐに住むことができます。
アーキビジョン21 石塚善光 製造部長
「トレーラーにフレームを載せて、載せたまま組み立てしている工場です」
「動く仮設住宅」の開発に取り組んだきっかけは、12年前の東日本大震災でした。
アーキビジョン21 石塚善光 製造部長
「住まいが流されて住むところがない。応急仮設住宅では住み慣れた土地から離れたりとか、壁が薄くて寒かったりとか、隣りの人の話し声が聞こえたり、住みづらいという要望がありました」
東日本大震災では、被災者が遠くに暮らす親族や知人のもとに身を寄せ、その土地で生活を立て直さざるを得なくなるケースがありました。「動く仮設住宅」は、小学校の校庭ぐらいの土地を確保できれば2週間ほどでおよそ30世帯分を設置できるため、地域コミュニティの維持が期待できると言います。
2018年の胆振東部地震でも「動く仮設住宅」が活用され、高校の仮設寮や「牛たちのそばに住みたい」という酪農家の要望に応えました。
震災から12年。いま、全国で「動く仮設住宅」の拠点づくりが進められています。
アーキビジョン21 石塚善光 製造部長
「仮設住宅の備蓄ですね。被災者の方が安心して次の生活に移行できる形でスピーディーな対応ができるようにしたい」
3月9日(木)「今日ドキッ!」午後5時台で放送
注目の記事
"理想の条件"で選んだ夫が消えた…27歳女性が落ちたタイパ重視の「恋の罠」 20代の5人に1人が使うマッチングアプリ【前編】

意外と知らない「鼻うがい」痛い?効果は?どうやるの?【THE TIME,】

今後10年で50~100大学が募集停止!? 「短大はさらに影響大」どうなる大学の”2026年問題” 進学者減少で大学の生き残り策は

「拒否という選択肢がなくなり…」13歳から6年間の性被害 部活コーチに支配された「魂の殺人」の実態

「なくしたくないし、撮り続けたい」日本一標高が高い鉄道 中学生が写真で魅力を伝える 赤字路線のJR小海線

20代の需要が4倍に!なぜ今「漢方」が選ばれるのか?ニキビやストレスに…SNSで人気広がるも専門医は “自己判断”への警鐘鳴らす

最新【壁の中から遺体】常連客の20代女性か ベニヤ板をはがすと服を着たまま…年始営業でバー経営の49歳男「何か臭いますか?」空気清浄機が4~5台

祝「成人の日」おめでとう!2006年はどんな年だった?駒苫甲子園準優勝「シンジラレナーイ」ファイターズ日本一、佐呂間町で竜巻、旭山動物園フィーバー…映像プレイバック

話題の『江戸走り』考案者の大場克則さんが解説“なんでやねん”と“パンチ”そして“パカパカ”…2年後「東海道五十三次」(江戸⇒京都)500キロ走破に挑戦へ
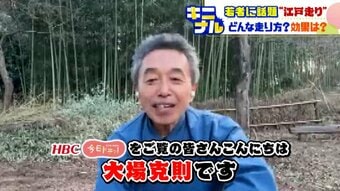
「スキー客が宙づりになっている」スキー場のリフトが停止するトラブル、13歳の女子中学生が負傷 北海道小樽市・スノークルーズオーンズスキー場






