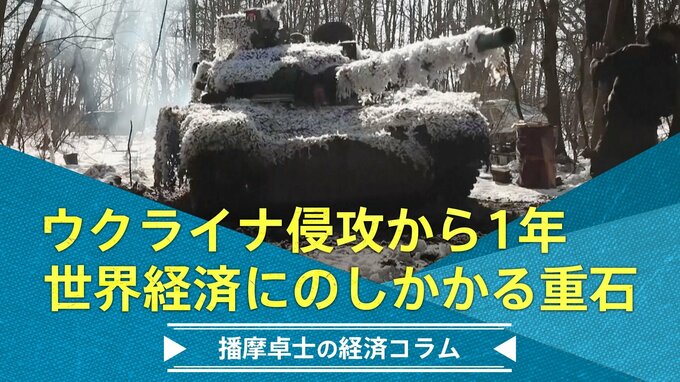ロシアによるウクライナ侵攻から1年が経ちました。現代では起こりえないと思われていた「古典的な戦争」が目の前で続いています。しかも、未だ停戦の気配すら見えません。この間、この戦争が世界経済に課した重荷は強烈で、1年を経て、その構造的な変化は、当初の予感以上に、「不可逆的」になったように見えます。
エネルギーや食糧高騰でインフレ到来
この戦争の影響が最も直接的に表れたのがインフレでした。ロシアからの原油や天然ガスを市場から締め出したことで、供給不安から価格が跳ね上がりました。広範なエネルギー価格の高騰は各国でインフレに火をつけ、欧州では10%、アメリカでは9%、日本でも4%台の歴史的なインフレ率を記録しました。
一時、1バレル=110ドルを超える水準まで跳ね上がった原油価格は、中国の経済不振や景気減速懸念などから、現在は侵攻前の80ドル前後に戻っていますが、脆弱な供給体制が続いています。より深刻なのが、天然ガスです。この冬は、心配された欧州が暖冬だったことに救われましたが、備蓄に向かない天然ガスは、供給そのものが足りなくなる恐れがあることに変わりありません。日本も未だロシア・サハリンからの天然ガス輸入に一定程度、依存しており、エネルギー危機と背中合わせのままです。
また世界の穀倉地帯が戦場になったことで、小麦に代表される穀物価格が上昇しただけでなく、中東やアフリカでは「食糧危機」さえ招きました。ロシアやウクライナを主産地とする肥料など、特定の商品価格も高止まりしています。
世界中のどこからでもコストの安いものを自由に輸入できるという「グローバル化」の時代ではなくなってしまったのです。それは、世界的な低インフレの時代に終わりを告げるものでした。
ロシアに寄り添う中国
より厄介なことことは、世界経済からのロシア除外と、米中対立がシンクロしながら進んでいることです。米中対立そのものは、ウクライナ侵攻前からすでに始まっていましたが、この1年、中国がロシアによるウクライナ侵略を批判さえせず、逆に「ロシア寄り」の姿勢を鮮明にしたことで、「西側経済」と「強権政治グループ」との経済分断に拍車がかかっています。先端技術はもちろんのこと、コロナ禍で課題が浮き彫りとなった、サプライチェーンの見直しも、国際経済にとってはコスト増の要因です。
インフレで「低金利時代」も終焉
低インフレ時代からインフレの時代になった結果、世界中が金利を引き上げざるを得なくなりました。アメリカの中央銀行FRBは、0.75%という異例の「3倍速利上げ」を4回連続で行うほどの急激な引き締めを行い、今なお引き締めを続けています。金利の引き上げは、どこかで必ず成長の鈍化を引き起こします。低インフレによって実現可能だった「低金利時代」も終わりを告げました。
高まる財政依存と支出増大
こうした中、自然と財政への依存が高まっていきます。。日本のガソリンや電力料金補助金に代表されるように、生活を直撃する物価高対策が短期的に必要になります。金利がなかなか下げられない中では、景気刺激の手段として、財政支出も求められることになるでしょう。
そして何より、戦争の脅威を目の当たりにした各国は軍事費の増強を迫られています。ロシアこそが最大の脅威であることを目の前に突き付けられた欧州諸国の軍備増強はもちろんのこと、極東の日本ですら防衛費倍増を決定する時代になりました。
金利が高くなった分、国債発行コストも高まるわけですが、それでも財政支出を増やさなければならないという、政策の舵取りが難しい時代に入ったのです。
「グローバル化時代」は、歴史の彼方へ
侵攻から1年を経ても、戦争は終結どころか、停戦すら見えません。仮に停戦があったとしても、ロシアからエネルギーや食糧がどんどん買えるような、かつての世界には戻らないことを、もう誰しもが認識しています。つまり、世界経済の、この構造変化は固定化しそうです。旧ソ連圏や中国から、コストの安いモノや人材、さらには工程までも、好きなように調達し、低インフレと低金利を謳歌した時代は、すでに歴史の彼方です。
この重石を背負いながら、成長を実現するためには何が必要か。経済政策の知恵と力量が一層、問われる時代です。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)