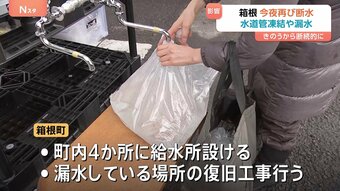円安が急速に進む中で注目された日本銀行の金融政策決定会合(4月27,28日開催)は、予想通り、現在の大規模緩和政策を維持することを決めて終了しました。円安が進んでも政策は変えないという宣言です。それどころか、長期金利を上限としている0.25%以下に抑えるために、毎日でも『指し値オペ』を行うと新たに宣言し、金利抑制の姿勢を一段と鮮明にしました。これを受け、外国為替市場では、日米の金利差拡大が決定的になったとして、ついに節目の1ドル=130円台まで円安が進みました。
日銀は同時に発表した物価見通しで、今年度の物価上昇率を1月時点の1.1%から1.9%に大幅に上方修正しました。念願の物価2%上昇にほぼ近づくにも関わらず、頑なにまで政策を変えず、金利を抑制し続けるのはなぜでしょうか。
第一に、日銀は現在の物価上昇は、賃金上昇を伴わない『一時的な』ものと見ているからです。エネルギー価格高騰の押し上げ効果が薄まるにつれて、2023年度にはプラス1.1%にまで上昇率が戻ると見通しています。第二には、現在も日本経済はコロナ前のレベルには回復しておらず、依然として『需給ギャップ』が存在しているからです。このタイミングでの金利上昇は景気を下押しするリスクが高いと考え、生産や消費、さらには所得回復までもう一押しして、好循環実現につなげたいという思いなのです。そうした考え方に偽りはありません。ただ、関係者の間では、「いったん長期金利の上昇を認めたら、その上昇が止められなくなると、日銀が恐れているのが本当の理由ではないか」と指摘する声も聞かれます。
日銀の現在の金融政策は、短期金利をマイナス0.1%にし、長期金利=10年物の国債の利回りを0%プラスマイナス0.25%以内にするというものです。元来、中央銀行の金融政策の対象は短期金利であり、日銀もかつては「幅広い要素で決まる長期金利はコントロールできない」と主張していましたが、様々な事情があって、長期金利も対象に加えたという経緯があります。短期金利の動向だけでなく、成長予測やインフレ期待などの結果として決まる長期金利を、今や『指し値オペ』という最終兵器によって力ずくで0.25%以下に抑え込んでいるのです。そのタガをはずしたら、世界的に金利上昇の中で、限りなく上限を試され、催促されるかのように金利高騰を容認せざるを得なくなりはしないかという心配があるのです。
長期金利が上がって一番影響を受けるのは、最大の債務者である政府です。国債の金利負担が急増すれば、財政が持たなくなってしまいます。もちろん、そうしたリスクが目先の政策変更で直ちに現実になるわけではありませんが、日銀は市場に委ねる怖さを感じていることでしょう。黒田総裁の就任以来9年、大規模緩和政策で「国債市場は死んだ」と言われるほどに、市場が自律的に価格(=金利)を決定する機能は著しく弱められました。市場機能を失わせたツケが、日銀に回ってきていると言えるかもしれません。
注目の記事
「足元固めないと党勢広がらない」庭田幸恵参議院議員が政治塾スタートへ “党勢拡大”・“候補者発掘”目指す 県内の野党国会議員は庭田氏1人に 富山

自民「316議席」で歴史的大勝 高市氏が得た“絶対安定多数”とは?中道の惨敗で野党どうなる【Nスタ解説】

雪かきで大量の雪の山…「道路に雪を捨てる」行為は法律違反? SNSで物議、警察に聞いてみると…「交通の妨げになる」罰金の可能性も たまった雪はどうすればいい?

時速120キロで飛ぶ“段ボール!? 修理はガムテープで 安い・軽い・高性能な国産ドローン 災害時の捜索や“防衛装備”への期待も

学校でお菓子を食べた生徒を教員12人がかりで指導、学年集会で決意表明を求められ… 「過剰なストレスで、子どもは瞬間的に命を絶つ」 “指導死” 遺族の訴え

増え続ける防衛費…安保政策「大転換」の是非 復興税を防衛の税に転用も 被災者の思いは【報道特集】