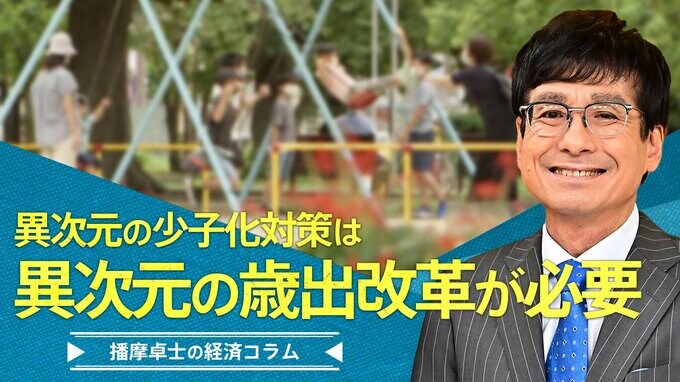子育て世帯への公的支援拡充
国会では連日、『異次元の少子化対策』についての議論が行われています。「児童手当の所得制限をなくすべき」とか、「児童手当より教育無償化の方が有効」とか、それぞれ一理ある議論です。去年1年間の出生数は、80万人を切る水準にまで落ち込みました。少子化が危機的に加速する状況で、出産や育児への「お金の心配」を少しでも軽減できるのであれば、子育て世帯への公的支援の大幅な拡充に踏み込むべきだというのが、コンセンサスになりつつあるようです。
財源論は4月の統一地方選挙の後に
問題は財源をどうするかです。児童手当拡充も、教育費の無償化も、毎年、兆円単位の予算が必要になります。これも「全額赤字国債で」というわけにいかないでしょう。4月の統一地方選挙の後には、財源探し、ひいては負担増の議論が始まることになりそうです。
でも、ちょっと待って欲しい。子育て世帯を支援するために、増税や社会保険料の引き上げをして、子育て世帯にも負担を求めるのはおかしな話です。富裕層にまで児童手当を支給するのに、低所得者の負担が増えるというのも、腑に落ちません。
生活者への直接支援の必要性増す日本
日本社会全体が貧しくなり、格差が拡大する中で、財政が「生活者」「消費者」に直接支援の手を差し伸べなければならないケースが増えてきています。少子化対策はその典型例です。世代を問わずに顕在化している貧困対策も、コロナの生活支援金も、消費を刺激するための旅行支援などのクーポン配布なども、皆、そうした「生活者」への支援です。今後もこうした政策の必要性は増すものと思われます。
そもそも日本の行政は、「生活者」「消費者」よりは、「生産者」や「供給者」に焦点を当てて、産業などの振興を図るために財政を使う、という建付けになっています。その証拠に、中央省庁は基本的には「生産者」「供給者」ごとの縦割りになっており、「生活者」に向き合う消費者庁やこども家庭庁ができたのは、ごくごく最近のことです。
政府が供給側(サプライサイド)に焦点をあて、その競争力強化に取り組むことは、もちろん重要な役割ですが、問題は、この「供給側縦割り方式」によって、補助金を含めた膨大な財政措置が延々と執られ続けていることです。一度始めた助成措置は、そう簡単にはなくならないのです。族議員などの「政」、縄張りをもつ「官」、そして恩恵を受ける「財」の、いわゆるトライアングルです。
供給側と需要側、両方の支援は無理
しかし、需要側(デマンドサイド)への公的支援が必要になれば、これまでと同じように供給側(サプライサイド)への財政措置をそのまま続けるわけにいかないのは、当たり前の話です。まして、日本はこの20年間、名目GDPがほとんど増えていません。そんな国で子育て支援を異次元にするとか、防衛費を倍にするとか、簡単にできるわけはないのです。
「生活者」「消費者」という需要サイドへの財政支出を増やすなら、「生産者」など供給サイドへの財政支出を減らすしか、道がないのは明白です。
異次元の歳出改革が必要
日本が成長期にある時には、供給サイドへの働きかけによって、供給力不足を解消し、さらには生産性を上げていくための強力な支援は、極めて重要でした。しかし、成熟国になった今は、むしろ、市場機能を通じて、需要の変化に応じた効率化や構造転換を進めることこそが求められおり、供給サイドへの財政支援の重要性は低下してるはずです。
『異次元の少子化対策』のための議論は、財政支出のあり方を抜本的に変える『異次元の歳出改革』につながることが必要不可欠です。『異次元』などという言葉を軽々しく使う時に、そうした覚悟はあるでしょうか。