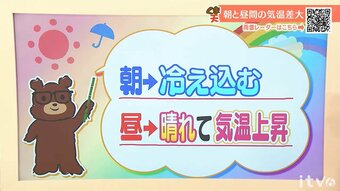少しずつ社会との接点を取り戻した鈴木さんは、当事者同士が繋がれる場所を作ろうと自助グループを設立。摂食障害の当事者をはじめ、生きづらさを抱える女性たちのための就労支援施設の運営もスタートさせました。
そして、社会全体に広く理解を呼びかけるシンボルとして、2018年、施設利用者らと共に手編みのリボンを制作。「摂食障害アクションデイ」や自助グループの全国大会などでPRを続け、愛媛発の「マゼンタリボン」は今、全国で啓発活動に役立てられています。

(鈴木さん)
「みんな誰かの友達だし誰か家族だと思うので、みんなが摂食障害をまず知る、浅くてもいいから知ることは、誰かを助けることかもしれないと思っている」
大学生や高校生、その親の世代が中心の地域ボランティアなど、幅広い年代に向けて発信を続けている鈴木さん。ここ数年、特に力を入れているのが子どもたちへの啓発活動です。

鈴木さんの支援機構が2018年度に愛媛県内33の医療機関を対象に行った調査では、最年少の初診の患者は7歳だったと報告されています。また、日本摂食障害学会の調査では、神経性やせ症(拒食症)の小中学生の新規患者の数が、コロナ禍前の2019年に比べて2020年、2021年と急増し、約2倍に上ったことも分かっています。
県内の児童・生徒へのアプローチとして、鈴木さんは2019年から県内の高校と松山市内の小中学校に、機構が制作したポスターやリーフレットを寄贈。2020年には、市内の教員向けの研修会も実施しました。