障害者雇用のルールに“改革” 「週20時間の壁」がなくなる
三宅さんのように「働きたくても就職先が見つからない」障害者は多くいる。
そこに立ちはだかるのは“週20時間の壁”の存在だ。
国は障害者の働く機会を広げるために民間企業に従業員のうち2.3%は障害者を雇うことを義務付けている。しかし、厚生労働省の調査では、2022年6月時点で、この法定雇用率を満たして障害者を雇用している全国の企業は48.3%と半数にも満たない。この数字から企業で障害者の働く環境の整備が進んでいないことが窺える。一方で、雇用率に反映できるのは1日平均4時間以上といった「週20時間以上働ける人のみ」という制度上の壁も存在するのだ。
そのため、障害者が週20時間未満で働ける採用枠は少なく、短時間しか働けない障害者の就職はなかなか進んでいないのが実情だ。三宅さんの場合も、新しい環境にゆっくりと慣れる必要があるため、「いきなりの長時間労働はハードルが高い」と施設の橋本一豊理事長は指摘する。

このような声を受け、“週20時間の壁”が取り払われることになった。2022年12月に成立した障害者雇用促進法の改正案では、勤務時間が週20時間未満でも雇用率に反映できるように定められた。重度の知的障害・身体障害者、また精神障害者を対象に週10時間から20時間未満の勤務で、「0.5人」分と算定される見通しだ。
三宅さんも対象になる予定で、制度が変わることを知って、“超短時間雇用”の採用が始まれば、「チャレンジしてみたい」と意気込んだ。
統合失調症の伊藤さん “絶望”乗り越え短時間雇用から正社員に「周りが気遣ってくれたから」

この変化を受けて、不安を抱えながらすでに企業で働くことができている障害者からも、歓迎の声があがる。
東京・江戸川区の会計事務所、古田土会計で働く、「統合失調症」の伊藤勇男さん(取材当時46歳)。
伊藤さんは新卒でタイヤの部品を作る工場に就職した後、清掃会社に転職したが、どちらも数年で退職に追い込まれた。週5日始発で仕事に向かうなど長時間労働が原因で体と気持ちがついていかなくなったという。辞めた後は、徐々に家の外に出るのも億劫になっていって、実家に引きこもって暮らしていた。そのような生活を6年続けた34歳の時、幻覚や幻聴などの症状が出始めた。心配した家族に病院へ連れて行かれた結果、統合失調症と診断された。「気持ち的には絶望しかなかった」と振り返る。
統合失調症 古田土会計で働く伊藤勇男さん(取材当時46歳)
「妄想の中での幻聴がほぼ24時間聞こえていた。知らない女の人の声が聞こえたり、宇宙人が見えたり。無気力で食べられない、眠れない、何もやる気が起きない。当時はつらかった」
薬を飲みながら通院を続け症状は落ち着いたといい、約2年後には古田土会計で短時間雇用から働き始めた。しかし、働いていない期間が長く、社会復帰は大変だったと話す。
伊藤勇男さん
「最初は働くだけでもすごくハードルが高い。ただ働くだけではなく不安感とか、『ちゃんとしないといけないのでは』と焦りもあった」
今では正社員として障害のある後輩社員を指導するまでに回復。この10年間、辞めることなく働き続けられている秘訣は、働き始めの頃に周囲が「働く時間を気遣うサポート」をしてくれたからだという。
伊藤勇男さん
「早く正社員になりたかったので働く時間を延ばそうと思っていたが、逆に周りの方に抑えていただいた。いやいや、まだそんなに焦らないで、ちゃんと長く働くんだからゆっくり時間を延ばしていきましょうと。すごく定着に良かった」
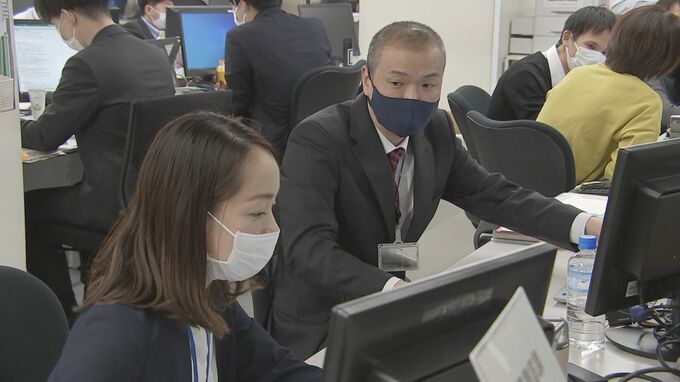
今でも毎朝、精神安定剤を飲み続けていて、再発のリスクの存在もあり、体調の波が大きい精神障害者にとって短い時間で無理なく働けるようになる今回の制度改革を歓迎する。
伊藤勇男さん
「いつ再発するか少し不安。若い時から年数が経っているので再発したら今度は週20時間働くことは難しい。(今回の制度で)短い時間から自分のペースで働けることは非常にありがたい。週20時間働けない人でも別に怠けているわけでも緩んでいるわけでもなく、精一杯頑張っている人はいっぱいいる」

















