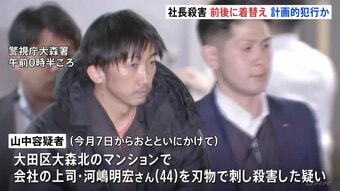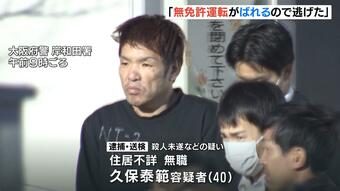2023年が始動しました。年初には「今年の経済を占う」のが常ですが、今年は、ひときわ予想の難しい年です。マクロ経済に関する「変数」が多すぎるからです。インフレが収まるのか、アメリカの利上げがどこまで続くのか、景気後退がどの程度になるか、日銀の政策修正がさらに進むか、など、予想の前提となる設問が多く、かつ、いずれも難問です。
■アメリカのインフレは思ったほど下がらないか
その起点になるは、やはりアメリカのインフレが収まるかどうかでしょう。アメリカの11月の消費者物価は前年比で7.1%上昇と、一時の9%台からは下がってきました。しかし、労働市場は引き続き逼迫しており、サービス価格や家賃の上昇は続いています。
BS-TBSの経済番組「Bizスクエア」で行った恒例の新春相場予想会に参加したアナリストの方々からも、「アメリカの今のインフレは、粘着力が強く、思ったほど下がらないだろう」との声が聞かれました。
インフレが思ったほど下がらなければ、中央銀行のFRBは、金融引き締めの手を緩められません。引き締めが続けば、景気の悪化は避けられません。ちなみに「今年中にFRBが利下げに転じる」とみるアナリストは、9人中、1人もいませんでした。
■日本のインフレも思ったほど下がらないか
インフレが思ったほど下がらない、というのは日本でも起きる可能性があります。11月の日本の消費者物価は前年比3.7%の上昇でした。日銀が目標とする2%をすでに大きく上回っています。しかし、日銀の黒田総裁は、「今の物価高は、輸入原材料や円安によるコストプッシュによる一時的なもので、今年度中には2%を下回るようになる」としています。
確かに、円安は一時より是正され、世界的な景気減速でエネルギーなどの原材料価格も下落に転じれば、そうしたシナリオもあるでしょう。その一方で、国内での価格転嫁はまだまだ続いていて、帝国データバンクによれば、今年4月までに食品7000品目以上の値上げが予定されています。春闘で高めの賃上げが実現した企業は、価格転嫁の動きをさらに続ける行動に出るでしょう。それこそが、目指していた「物価と賃金の循環」なのです。
仮に、物価上昇率2%以上が長く続くのであれば、日銀は異次元緩和を継続する根拠を失ってしまいます。それは金利の急騰も招きかねません。それ故、日本のインフレも、今年の経済の大きな「変数」です。
■物価高で実質賃金は大幅減
インフレが思ったほど下がらない、となると、生活はますます苦しくなります。6日に発表された最新の毎月勤労統計によれば、物価変動の影響を考慮した、11月の日本の実質賃金は、前年同月比で3.8%もの減少でした。この下落幅は8年ぶりの大きなもので、実質賃金の減少は8か月連続です。ここで賃上げがなければ、経済は回りません。
岸田総理は、財界の新年パーティーで「インフレ率を超える賃上げを」と要請しました。さらに、「今年の賃上げの動きによって、日本経済の先行きは全く違ったものになる」とまで踏み込みました。全く、同感です。
■岸田政権は可処分所得を増やす政策を
だとすれば、岸田政権は、それと整合性のある政策を採るべきです。防衛費増額を賄うために、事実上の所得税増税を打ち出し、安易な雇用保険料の引き上げを容認し、異次元の少子化対策のための増税まで検討するなどというのは、全く誤ったメッセージです。国民の可処分所得を減らす政策に、安易に乗ってしまう政権に、賃上げを求める資格はありません。
播摩 卓士(BS-TBS「BiZスクエア」メインキャスター)