「第三者は無力な存在では決してない」
明確に章立てはされているが、通奏低音となっているテーマは、第1章で小椋聡さんが記した一文に凝縮されている。「この事故から私たちが学ぶべきことは、社会安全を構築することの重要性のみならず、利便性と豊かさを追い求める社会の中で、事故の教訓をとおして私たちが何を大切にし、日々を『どう生きるのか』を問い続けることである」
そしてその通奏低音は、脱線事故と大震災という、事故と災害の差異も越境している。「Team大川 未来を拓くネットワーク」という団体の代表として、東日本大震災や大川小に関する活動を続けている只野哲也さんは、“どうして活動を続けるのか”という問いを投げかけられる点について、こう心境を記す。
「結論、辛いし悲しい。まだ何も乗り越えられていない。これからもおそらく変わることはない。(中略)理不尽なことだらけの現実から逃げ出したくなることもあったし、メディアの取材を受けられなくなったこともあった。大川から離れて何もかも忘れて普通に生きたいと考えることもあった」
「それでも、何度打ちのめされても続けていこうと奮起できたのは『家族』がいたから。3月11日は亡くなった母の誕生日でもある。可愛がってくれた祖父のことも、いつも一緒にいた妹のことも忘れるという選択肢は私にはない。うやむやにすることはできないのだ」
「自分が自分らしく生きるために、大川と向き合い続けているということになる。大川との向き合い方に『納得』できたとき、私は本当の意味で新たな自分の人生を歩むことができるのではないかと思っている」
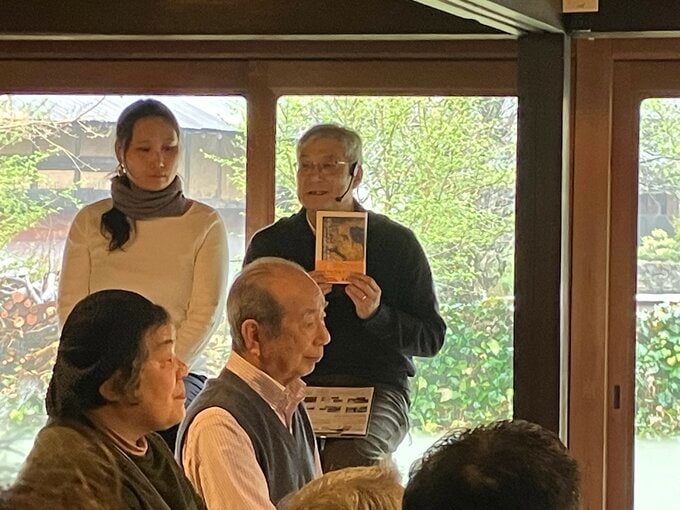
そのうえでこの本は、『どう生きるのか』を問う営みにおいて、“当事者ではない人々”が果たす役割の意義を高らかに謳う。脱線事故とは直接的な関わりのない立場から、ゼロから展覧会を企画し、去年のシンポジウムにも参画した木村奈緒さんのメッセージは、事故から20年経った今、ストレートに心に訴えかけてくるものがある。
「ある体験を『わたし』の中に留めるのではなく、『わたしたち』の体験にすること。そうすることで、たとえ当事者がいなくなっても、その体験や事象が生き続けて広がっていくのではないか。(中略)そのためには、出来事から『遠い』第三者の存在は欠かせない。第三者は無力な存在では決してない」
「立場や出来事からの距離の違いは、分断のための障壁になるのではなく、自分ひとりでは見ることのできない景色を見るための道のりであってほしい」














