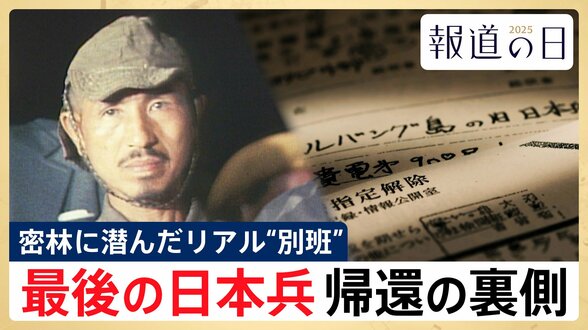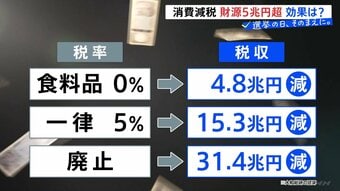■須江語録は、いかにして生まれたか。学生コーチ時代の“後悔”

チームを、選手を鼓舞する須江監督の言葉は、いかにして生まれたのか。その原点は、高校時代のある“後悔”にあった。
須江監督自身、仙台育英のOBだ。「野球をすることを職業にしたい」という夢を持って、地元埼玉を離れて入学した。しかし、初日の練習から大きな挫折を味わったという。
「レベルが高すぎて、選択を間違えたと。努力で差が埋まることはないんだなと思った。地元を離れた手前、そう簡単に挫折することはできなかった。格好悪いので。ただ、実際心の中では、僕は試合に出ることは1%もないなと思った」
技術力の高さ、やる気、すべてにおいてレベルの高いチームメイト。完敗だった。
そして、2年生の秋。「新人係」に任命された。事実上の「引退勧告」で、練習の機会が無くなることを意味した。他のチームメイトからの推薦もあり、「学生コーチ」に任命された。
強豪校に送り出してくれた親に、申し訳ないという思いが先にきて、本当はやりたくなかった。それでも、与えてもらった役割を果たそうと引き受けたが、うまくできなかったという。
「当時の自分には、とにかく想像力が無かった。チームを強くしたい、勝ちたいという思いで、人の言葉に耳を傾けず、一方通行の指導だった。モチベーションのない選手の気持ちの背景が分からなくて、怒ってばっかりだった。自分はやりたくない学生コーチをやっているいらだちもあって、厳しいことを言ったり伝えたりすることが仕事だと役割をはき違えていて、とても居心地が悪い環境を作ってしまった」
仲間がいなかった。ご飯を食べるときはいつも一人だったという。
自分が求められた役割を果たせなかったことに気がついたのは、記録員としてベンチ入りした高校3年生の夏だった。春の選抜準優勝をひっさげ、夏の甲子園にも出場。しかし、初戦で敗退した。練習の質が下がり、モチベーションに大きな差ができて、仲間との間に溝が生じてしまった。
「もっと私が間に立ち、言葉を尽くしてモチベーションが下がった選手に耳を傾けてあげれば、違った結果になったかも知れない。使命感だけで突っ走って、残した結果が右肩下がり。それにすごく後悔がある。その時の気持ちを忘れないように運営をしています」
学生コーチで得た苦い経験から、監督となった今、選手たちの言葉に耳を傾け、何に迷っているか、何を求めているかを聞くようにしている。そして、選手たちが求めている言葉を、投げかけるよう心掛けている。
「何を言うかはもちろん、いつ言うかが大事だと思っています。よく観察して、よくコミュニケーションをとりながらです。選手たちにいつも、『世の中、そんなに悪くないし、自分はそんなに低くないよ』と伝えている。『当時の僕と比べたら、君にはこんなに才能がある、良いところがあるよ』『諦める理由がない。すべて自分次第だ』といつも言っている」
取材の最後に、「監督の面白さ」を聞いた。
「とてもシンプル。生徒の成長を、人間の成長を身近に感じること。同じ子かなって思うような成長を感じる時がある。仲間との衝突だったり、理解しあえた時だったり、成功体験かもしれない。それを感じることが喜びだし、すごいなと思えることが楽しみです。だって、感動するじゃない」
須江監督はそう言って、恥ずかしそうに笑ってみせた。
「TBSテレビ 報道の日2022」
ディレクター・神保圭作