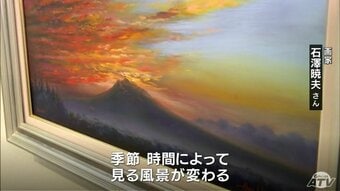青森県黒石市の津軽烏城焼で、2026年の干支「午(うま)」のぐい呑みが焼きあがりました。
陶芸家が窯を閉じていたレンガを外し、焼き上がった食器を1つずつ慎重に取り出します。その中に、たてがみや大きな鼻が付いた「午」の陶器がありました。
須崎 蓮 記者
「こちら、午の置物にも見えますが、逆さにすると『ぐい呑み』になります」
黒石市の津軽烏城焼は毎年、干支のぐい呑みを製作しています。
2026年の干支「午」のぐい呑みは10月23日から5日ほど窯で焼き、1週間かけて徐々に温度を下げ、4日に窯出しとなりました。
110個焼いて、割れたり、一部が欠けたりせずに残ったのは8割にあたる90個ほどで、上々の出来だということです。
津軽烏城焼 陶工 今井瑩典さん
「今回頭が重いので、横に転ぶか心配していたが、焼きも良くて抜群だと思う」
津軽烏城焼の特徴は薬を使わず、陶器に降りかかる薪の灰で白みがかった模様を生む「自然釉(しぜんゆう)」です。
これを生み出すため、1回の焼きで使う薪は一般的な量の倍となる約15トンです。
焼き上がったぐい呑みも一つとして同じ模様はなく、すべて表情が異なります。
津軽烏城焼 陶工 今井瑩典さん
「家族と一緒においしいお酒を飲んで、また来年1年を健康に暮らしてほしい」
完成した午のぐい呑みは、約7割が予約済みです。
津軽烏城焼で11月9日~16日まで開かれる「窯出し市」で約20個が限定販売されます。