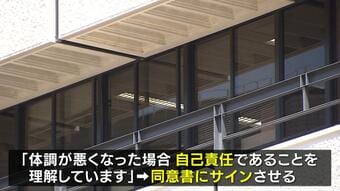■実質賃金の目減りで、大幅賃上げ要求
6日に発表された10月の毎月勤労統計調査によれば、物価変動を考慮した実質賃金は前年同月比で2.6%もの減少となりました。名目賃金は1.8%上がったものの、実質賃金算出のための物価が4.4%も上がったため、差し引き2.6%ものマイナスとなったものです。実質賃金のマイナスは、今年4月以降、7か月連続で、2.6%ものマイナスは7年ぶりの大幅なものです。物価上昇に賃金が追い付かず、生活が苦しくなる状況が深く、長くなってきています。
こうした中、来年の春闘での賃上げはますます重要になっています。連合は、定期昇給を含めて5%程度という1995年以来28年ぶりとなる高い要求を掲げました。相場のけん引役である自動車や電機などの労働組合で作る金属労協も7日、ベースアップを6000円以上とする、8年ぶりの高い要求方針案を発表しました。実質賃金が大きく目減りする中で、まさに労働組合の存在意義が問われる春闘です。考えてみれば、これまで働く人たちが「賃上げなし」でも我慢して来たのは、物価が上がらないという前提があったからです。そうした「お約束事」がなくなった以上は、高い賃上げを求めるのは当たり前の話です。
■経営側も賃上げに前向きだが、中小企業は余力小さく
これに対して経団連の十倉会長も、こうした高い要求に「驚きはない」とした上で、「(今年の春闘の賃上げ実績の)2.27%を超えて欲しいし、超えなくてはならない」と、異例の前向きな発言を行っています。景気の回復や円安の恩恵を受ける大企業では、長年にわたって蓄積した内部留保もあることから、大幅賃上げを期待したいところです。
その一方、中小企業では、原材料コスト高騰の価格転嫁が大企業ほど進んでおらず、むしろ経営環境は厳しくなっているところが少なくありません。賃上げ余力がない中では、「ない袖は振れない」という形に終わるリスクもあります。賃上げを広く実現するためには、この価格転嫁こそが、最も重要なポイントです。政府はすでに、賃上げを行った企業への法人税減税などを制度化していますが、そこに留まらず、こうした価格転嫁が円滑に行えるよう後押しする政策にも大胆に踏み込む必要があるように思います。価格転嫁が直ちに実現しなくても、近い将来に価格転嫁(つまり商品価格の引き上げ)ができそうだと思える環境にすることも必要です。
■日本に染み付いた「ゼロインフレ・ノルム」
日本では、この20年以上にわたって、「ゼロインフレ・ノルム」が染みついてきました。「ゼロインフレ・ノルム」とは、先ほど述べた「お約束事」のこと。つまり、企業も消費者も「ゼロインフレ、つまり物価が上がらないことが当たり前」と信じて疑わず、あたかもそれが社会規範のようになっていた状態です。働く人は「来年も物価は上がらない」と信じ、大した賃上げ要求をせず、企業は「来年も賃上げなし」と決めてかかり、商品価格引き上げは想像すらしない、という世界です。物価の実証研究の第一人者である東京大学の渡辺努教授の言葉を借りれば、「物価も賃金も凍り付いた状態」が長く続いてきたのです。2013年以来のアベノミクスや異次元緩和によっても、この「ゼロインフレ・ノルム」を溶かすことはできませんでした。
■インフレ予想が、「物価と賃金の好循環」につながるか
それが今、外部から侵入した輸入インフレによる物価高を通じて、動く気配が見えてきています。人々の、物価上昇予想(期待)が急速に高まってきています。この「予想」こそが、物価にも賃金にも重要なことです。物価が上がると予想するからこそ、労働者は賃上げを求め、同時に個々の商品の価格上昇を受け入れるのです。企業も、物価全体が上がると予想するからこそ、自社の商品価格を引き上げることができ、その予想があるからこそ、賃上げに応じることができるのです。
今回の起点は、まず、輸入インフレによって物価が上がったことです、次に労働者が賃上げを要求しました。その次に来なければならないのが、企業が賃上げに応じることです。これができれば、賃上げした分の価格転嫁(つまり商品価格の引き上げ)が行われ、再び物価が上昇するという「物価と賃上げの好循環」につながる可能性が出てきます。賃上げこそが最大のポイントであり、最大の難所です。
難所ですから、その難しさを指摘することは簡単です。しかし、長年、実現できなかった「2%の物価上昇」というチャンスは、みすみす見逃してしまうにはあまりにもったいないと思うのです。物価も賃金も上がる『普通の経済』に戻るために、何とか、この機を活かせないか、まさに各界各層が知恵を絞るべき時のように思います。
播摩 卓士(BS-TBS「BiZスクエア」メインキャスター)