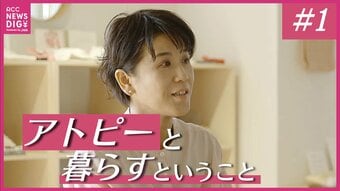「増産」方針でも「米が作れるわけがない」理由は・・・
日名内下町内会 水野克成会長
「ここは去年は作りよったんだけど。今年はもう川の水は使えんいうことで、もうやめたって。この辺の田んぼはね」

この日も、川は泡立っていました。水の異様な状態は、この地区でも、2024年6月以降、度々目撃されています。
日名内下町内会 水野克成会長
「黒かったんじゃ、青黒い、青黒い水やった。で、泡がすごかった」
Q. どんなお気持ちになりました?
「これはもう米は作れんな、こがな(こんな)水を使うて米が作れるわけがなかろうが、と思うた」
日名内下地区でも、今年春、別の谷水を運ぶ水路が整備されましたが、水が届かない部分もあり、作付け面積は減りました。日名内地区全体で、510アール中、半分以上の265アールで作付けができなくなり、3軒の農家は完全に稲作を出来ない出来ない状況です。
日名内下地区に住む林達志さん
「(手を水に)入れた時、すごい臭かった、こっちが入れた方が。で、私の体臭かの思うてからも、こっち入れたら、こっちも上げた瞬間に臭かった」
水質悪化を実感した林達志さん(74)は、これを機に米作りをやめてしまいました。
日名内下地区に住む林達志さん
「コンバインも処分して」
「もうこれ以上やっても、ああいう上の産業廃棄物の汚水いうものが解決せん限りは、もう作らん方がいい」

代々この土地で米を作ってきた町内会長の水野克成さん(75)は、地域の未来を案じています。
日名内下町内会 水野克成会長
「農家なのに、自由に米を作れないというのは、もう寂しいよね、いずれはここにもう住めんようになるんじゃないかな、と思う。死んだ川になるけんね」

全国同様、広島県内の水稲農家の数は、30年間で4分の1に激減しています。さらに面積的には、全国(4割減)よりも減少率が激しく、6割も減っています。
「生産量を増やす」という政府の号令とはうらはらな実態が、日名内地区では加速していると言えます。
一方、この事態に関心を示す人達も増えています。