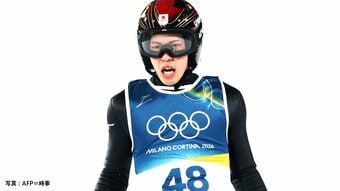「クマでなく人が変わった」ヒグマを人慣れさせた“人間側”の無自覚な行動

知床財団職員
「こらー!ダメだ、エサやったら」
知床のヒグマを人慣れさせたのは、“人間側”だと指摘する声もあります。

ポイ捨てされたゴミ袋をくわえるヒグマ。一度、人の食べ物の味を覚えたクマは、食べ物を奪おうとしたり、車などに侵入したりするようになるといいます。
地元住民
「(Q.今と昔の変化は)クマよりも人なんじゃないですか、きっと。食べ物が美味しかったら、そりゃ出てくるんだから、食べ物与えないとか、そういうことを住民は知ってるけど。結局、観光客は動物園感覚で来るから。人間が変わったんじゃないですか」
山小屋の管理人も、“人慣れを加速させる人間”の存在を指摘します。

羅臼岳の山小屋管理人 四井弘さん
「河口の方にいる(エサの)カラフトマスを捕まえるクマの写真を撮る人が、めちゃくちゃ多い」
知床国立公園内の、ヒグマが多く出没するイワウベツ川。人々の視線の先にいるのは、エサを獲りに来たヒグマです。

羅臼岳の山小屋管理人 四井弘さん
「本当に多い時は100人以上のアマチュアカメラマンが集まって、クマが出てきたってなったら、みんなで一斉にクマに近寄って写真撮るわけ。人間にバーッて囲まれたら『人間ってあんまり怖くないんだよね』というのは(クマが)必ず学習していると思う」
現在、自然公園法では、ヒグマなどの野生動物への付きまといや過度な接近が禁止されています。
9月、この場所には“クマ待ち”を防ぐ目的で監視カメラが設置されました。
知床財団 玉置創司 事務局長
「『できる限り距離を取ってくれ』というのは広報はしていますし、いろんな看板を立てていますけど、なかなか守られないのが現状」

人間の無自覚な行動がクマの人慣れを招く。その結果、本来必要なかったはずの駆除が発生しているのが現実だといいます。
知床財団 玉置創司 事務局長
「人を恐れなくなった個体というのは、やっぱり距離感が失われていて、そこを適切な距離に戻せる個体はおそらくいないと思います。
近づく行為というのは、エサやりとあまり変わらないと認識していただいた方がいいのかもしれない。その後、皆さんはもしかしたら知ることはないかもしれませんが、知床ではその個体が駆除されているという現実もあります」