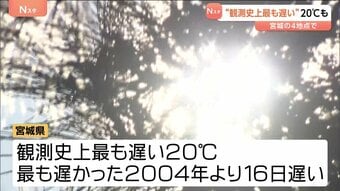大学の「こども心理学部」へ
――資格取得後、さらに大学で子どもの心理学を学ぼうと思ったきっかけは何でしたか?
つるの剛士氏:
資格と免許を取って嬉しかった反面、目標を失って、燃え尽き症候群のような気持ちになりました。この後どうしようかと考え、こども心理学を学べる大学があったので、行けるかもしれないから軽い気持ちで行ってみようと思いました。蓋を開けたら全くわからない世界で、勉強するつもりじゃなかった。思っていたことと違っていた。しかし、やってみると面白くてはまってしまいました。だから「寄り道」です。
ミッドライフ・クライシス(中年の危機)に陥った
――どんな部分にはまったのですか?
つるの剛士氏:
40代後半で「ミッドライフ・クライシス(中年危機)」に直面しました。それまでネガティブなんて知らない、まっすぐどこまでもポジティブだった私が、47歳ぐらいの時に陥って、ネガティブになりました。コロナ禍で、テレビや芸能界の在り方も変わった。テレビというものに夢を持っていて、そこでしか仕事をしてこなかった。そしてネットやYouTube、若い人の台頭で、それまでの芸能界の価値観がガラッと変わった。その中で「自分って何なんだろう」とぶち当たった。そしたらすごくネガティブになって、もう一人の自分が出てきて「お前、ネガティブじゃん」って声かけてくる。それで結構落ち込んだ。
――寝る前に思い出すとか?
つるの剛士氏:
寝れなかったです。1時間で目が覚めて。それで妻に心配され、いろんなこと話したら涙が出てきた。そんな姿を見たことがない妻が内緒で、医者に相談していた。そしたら軽い鬱状態かもしれないと言われ漢方薬を出された。そのときに「お疲れ様、大丈夫ですよ」といったメッセージが書かれていて、また泣いた。結局その薬は飲みませんでしたが、心理学を学ぶ中で、「中年危機」が出てきた。学問になっていて、みんな経験しているし、誰かが解いてると思ったら、またどっぷり入ってしまった。それが分析心理学といって、ユングとかの世界。
学問ってすごい!“中年の危機”の理由が心理学の中にあった!
つるの剛士氏:
人間ってやっぱり生きてる中で、意識してる部分と、無意識の潜在意識の部分があって、これがちょうど今の年代になってくると、自我と潜在意識、いわゆる「自己(セルフ)」を認めて、今までの自分も、ありのままの自分でいい、これからそれをプラスしてどういう生き方をしていくのかという提示を受ける年代だ…みたいなことがもろに書いてあった。
これだ!と思ってそれでまた嬉し涙が出てきた。心理学というか学問すごい!と思った。
誰かがエビデンスとして実験してくれたり、自分の経験で苦しい思いをして、誰かがこれを助けようと思って学問にしてくれていることがあったんだと思った。「本当に学問っていいな」と単純だと思ったが、知っているだけでも安心した。これ僕だけじゃなくて、同じ年代のスタッフさんとご飯食べながらこんな話したら同じ悩みを持つスタッフと話すと、「実は私も」と何人かに共感され、これは僕だけじゃない。学問が誰かの苦しみを助けるためにあると実感し、大学に行ってよかったと思い、学ぶことで誰かを楽にできると気づきました。
大人になってからの「学び」とは

――私も50歳で大学院に行きましたが、政治記者として永田町の事象を外から説明できなかった。今思えば「クライシス」だったかも。その経験から学び直し、世界が100倍広がりました。大人になってからの学びは、人生の意味づけになりますよね。
つるの剛士氏:
若い時の学びは未来の準備ですが、大人の学びは経験の点を繋げ、点と点が繋がり、線になり、立体感が得て解像度を上げる感覚です。それが大人になって実際に学んでよかったと思うこと。
――SDGsもゴールを作らず、流れの中で学ぶのが大事だと思います。大人の学びはゴールがないですよね。