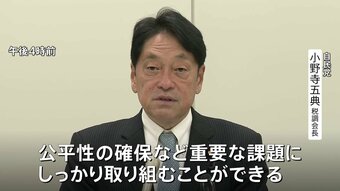■3人に1人があおり被害 恐怖と焦り…その時にすべき3つのこと
警察庁のアンケート調査では過去1年間に3人に1人があおり被害を受けた経験があると答えている。危険な「あおり運転」に遭遇してしまった際には、どう対応すべきなのだろうか?交通事故に詳しい菅藤浩三弁護士に話を聞いた。

――今回のような「執拗なクラクション」「車間距離を詰める」という行為にとても不安を感じたのですが、法的に問題がある行為だったのでしょうか?
菅藤浩三弁護士
「令和2年6月から、あおり運転そのものを取り締まる 『妨害運転罪』という新しい法律が成立しました。今回のケースだと『警音器の使用等』の違反、『車間距離の保持』の違反という点で『妨害運転罪』(あおり運転)に該当します。
まず『警音器の使用等』は、例えば“警告”のためにクラクションを鳴らす必要があることは分かりますよね。ぶつかりそうになった時など『危ない!』という意味です。それは『適切な利用』ということになりますが、それを超えて“執拗に”鳴らす、また、立体駐車場を上っている最中に鳴らし続ける必要はないわけですよね。
さらに車間距離も本来は極端に詰める必要はないですから「車間距離の保持」違反なわけです。
ただ『妨害運転罪」は公道を想定している法律なので、“それ以外”の場所で起きた行為に対して適用するかというとまだはっきりと詰められていません」
――なるほど。でも場所がどこであれ、被害に遭っているときは、パニックになってしまいますよね。不安と焦燥感で、事故につながりかねないと思いました。どう対応すべきだったんでしょうか?
菅藤弁護士
「危険なあおり運転にあった場合は必ず『停車して、ロックして、警察を呼ぶ』のが正しい対応になります。基本的にあおり運転をする人というのは、非常に興奮状態にあります。あおった相手が怒鳴ったり、ドアや窓ガラスを叩いたりするケースもこれまでありました。鍵をロックして、警察が到着するまでは車内から絶対に出てはいけません」
――警察が来ても、水掛け論になりそうな気もします。というのも、今回、私の車にはドライブレコーダーが前方だけで、クラクションの音は記録されているものの、後続車の車間を詰める様子までは記録されていませんでした。
菅藤弁護士
「正直に言ってそれだけでは証拠としては非常に弱いと思います。クラクションの音が録音されていたとしても、今回のように前方しか撮影されていないとなると、そのクラクションが後続車の鳴らしたものかが特定できないわけです。警察に相談する際には、加害者側のナンバーの特定も必要にになりますし、何よりも加害者が、言い逃れができなくなるための道具をどれだけ集めることが出来るか、ということが重要です」
――具体的には何ができるのでしょうか?
菅藤弁護士
「後方部分を、例えばスマートフォンで同乗者に撮影してもらうというのもひとつです。停車して警察を呼ぶ間も、相手が挑発行為を続けるようなら、その行為もすべて撮影して記録してください」
いつ遭遇するかわからない危険なあおり運転。もちろん、知らないうちに自分の運転がそのきっかけをつくっている可能性は大いにある。まずは自分の運転と周囲の車への配慮を再確認することが必要だ。そのうえで、万が一危険なあおり被害にあっても、相手に引きずられず、冷静な気持ちで「停車して、鍵をロックして、警察を呼ぶ」ことを忘れないようにしたい。