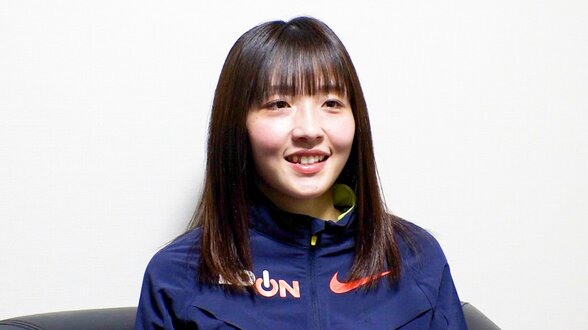大会6日目(9月18日)の男子400m決勝で、中島佑気ジョセフ(23、富士通)が44秒62で6位に入賞した(予選では44秒44の日本新もマーク)。この種目の入賞は91年に、同じ国立競技場で行われた東京世界陸上7位の高野進以来、34年ぶりの快挙だった。高野はその後の短距離・ハードル種目の日本の成長に、多大な影響を与えたレジェンドだ。その高野の域に中島がどう成長してきたのか。中島を学生時代から指導してきた東洋大の梶原道明監督(72)に取材した。
34年前の涙の理由は?
コーチが選手と接することができるのは、ウォーミングアップを終わって選手が召集所に向かうところまでである。梶原監督は中島を送り出した時、「半分泣いていました」と明かす。
「歳をとると涙もろくなりますね。そのあとはスタンドで見ていたのですが、ジョセフの名前がコールされて、ワーッというものすごい歓声が起きたときは震えました。震えて、涙が出ました。準決勝の後も、ジョセフが戻ってきて抱き合った時に涙が出ていました」
梶原監督は34年前にも同じ国立競技場開催の東京世界陸上で、今回ほどではないが涙ぐんでいた。兄の千秋さんが静岡県吉原商高時代に指導した高野進が、日本人短距離種目世界陸上初の決勝を走った(7位)。五輪を通じても400mでは初、短距離種目では1932年ロサンゼルス五輪男子100m6位の吉岡隆徳以来の快挙だった。梶原監督は競技役員として、高野の走りを目の前で見ていた。
「鳥肌が立ちましたね。泣いているつもりはないのに、自然と涙が出ていたと思います。兄の教え子が地元開催の世界陸上で歴史に残る快走をして、すごく感激したことを覚えています」
それから34年。今度は自身が指導した中島が、同じ国立競技場開催の世界陸上で決勝のレースを走った。高野以後何十人という日本代表が挑戦し、跳ね返され続けて来た舞台である。男子短距離3種目で決勝に進出した日本人選手は以下の3人(5回)しかいない。
91年:高野進400m、7位
03年:末續慎吾200m、3位
17年:サニブラウン200m、7位
22年:サニブラウン100m、7位
23年:サニブラウン100m、6位
梶原監督は年齢を理由に挙げたが、日本短距離界にとって本当に歴史的といえるシーンに、直接関わった。多くの指導者が同じように涙を流したのではないか。
大学2年時までは代表争いができなかった中島はどんな成長過程でファイナリストまで上り詰めたのだろうか。
高校時代の中島は目立った選手ではなかった。48秒05が自己記録で、18年の高校リスト193位というレベル。19年に東洋大に入学した。
梶原監督は当時を「その頃はヒザが良くなかった。成長痛で関節に負荷をかけると痛みが出たりしていました。ジャンプ系のメニューは軽めにしたりして、7割程度の練習でしたね」と振り返る。
1年時はU20日本選手権で6位に入賞した。その大会の予選で出した47秒54がシーズンベストだが、決勝では48秒12とタイムを落としている。「腰が落ちたフォームで、接地時にヒザや足首がぐにゃっと曲がるような動きでした。47秒中盤は当時の力から、妥当だったと思います」
2年時は6月のDenka Athletics Challenge Cupで46秒09(決勝1組1位)と、自己記録を1秒近く更新し、自身初めての46秒台をマークした。「300mまでは他の選手たちと並んでいたのですが、最後の100mで一気に抜けてフィニッシュしました。タイムは測っていませんでしたが、ラスト100mは12秒少しだったと思います」。東京2025世界陸上のラスト100mは、予選が11秒75、準決勝が11秒76、決勝が11秒85。ラストの強さが6位入賞を勝ち取ったが、その片鱗が当時から見られていた。
だが翌7月の日本選手権は、予選こそ46秒36のセカンド記録で通過したが、決勝は47秒18の8位。前年のU20日本選手権もそうだったが、決勝でタイムを落としている。
それに対して東京世界陸上は予選44秒44、準決勝44秒53、決勝44秒62と、3本全てで従来の日本記録(44秒77)を上回った。
「(2年時は)まだ力がありませんでしたが、ようやく色々な練習ができるようになってきた頃です。パワー系のトレーニングもして、ヒザや足首が潰れない動きができれば面白い選手になると思いました」
成長の兆しは感じられたが、この年に開催された東京五輪の代表争いには、まったく加わることができなかった。ファイナリストになる姿は、梶原監督もまったく想像できなかったという。