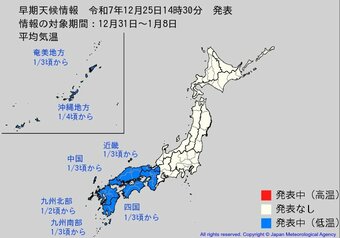冬の間に積もった雪を、夏の冷房に利用する。建物の中に雪を置いて、電気を使わずに日本酒を貯蔵する。豪雪地の〝厄介者〟である雪を、エコなエネルギーに変える取り組みが新潟県南魚沼市で進んでいる。「シリーズ SDGsの実践者たち」の第47回。
雪にシートを被せて冷房のエネルギーに利用
全国的に猛暑が続いていた7月下旬は、新潟県南魚沼市でも気温が30度を超えていた。南魚沼市役所を訪れると、シートが被せられた高さ3メートルくらいの堆積物が敷地の一角にある。看板には「スノーバンク南魚沼」と書かれていた。


シートに覆われているのは、冬の間に降り積もった雪。この雪を少しずつ解かして、解けた水をポンプでくみ上げ、冷房システムの冷却水に使われる不凍液を冷やす。この仕組みによって、市役所南棟の1階に設置された4台のクーラーが、雪のエネルギーによって稼働している。暑い外から一歩建物に入ると、ヒヤッとする涼しさを感じるほど、クーラーは十分に効いていた。


南魚沼市は新潟県南部の魚沼盆地に位置していて、南魚沼産コシヒカリの生産地として知られる。

その一方で、世界有数の豪雪地でもある。冬場は2メートルから3メートルの高さに雪が降り積もるのが当たり前の土地だ。一晩に1メートル近く積もることもあり、累計積雪量は毎年10メートルを超える。シートに覆われた雪がある市役所の敷地の一角は、もともと除雪したあとの雪をためておくスペースだった。
この雪をできるだけコストをかけずにエネルギーとして利用しようと、今年度から大阪のメーカーと共同開発した雪を保存するシートで実証を始めた。環境交通課の岩井英之課長によると、シートを被せた4月下旬には450トン、高さ5メートルの雪があったが、7月下旬のこの日までに90トンまで雪が解けたという。

「シートは15メートル四方の敷地に、450トンの雪を台形に整える前提で開発しました。シートには450万円、雪山の成型には150万円の費用がかかっています。今年は暑くて5月12日から冷房を使い始めたので、予想より早く雪が解けています。それでも、ドローンで測量をすると、雪山が全体的に縮んでいるのがわかっていて、理想的な解け方です。消えてしまう雪を少しでも長く残すシートの効果が出ていると思います」