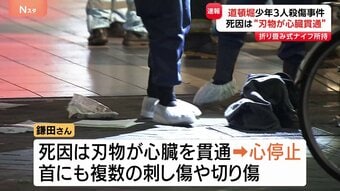あれから25年が経ちました。1997年11月24日、4大証券の1つだった山一証券は、2000億円もの簿外債務の存在を認め、自主廃業することを決めました。バブル崩壊で抱え込んだ含み損を簿外で処理し続けてきたものの、もはや隠し通すことが不可能になったのでした。名門証券会社の破綻は、バブル崩壊後の金融危機がクライマックスを迎えようとしていることを否応なく見せつけ、大企業は潰れないというサラリーマン社会の神話も崩したのでした。「社員は悪くありませんから」と涙ながらに述べた山一の野沢社長の記者会見の映像は、文字通り、時代を刻んだシーンです。
■平成金融危機は、より「深く」「長く」
97年の11月にはそれに先立って、三洋証券や北海道拓殖銀行が経営破綻し、不安心理が高まっていましたが、山一破綻でその不安はさらに広がりました。ひとつの危機がさらに大きな危機を呼び込むような展開で、日本の平成金融危機は、想定以上に「深く」「長く」なりました。翌98年には、日本長期信用銀行(長銀)と日本債券信用銀行(日債銀)が破綻、一時国有化されると、大手銀行にも信用不安が波及しました。当時、金融担当記者の一人だった私も、毎晩、灯の消えることのない日銀や大手銀行の本店を見上げては、日本発の金融恐慌に怯えたものです。
結局、日本の平成金融危機は、りそな銀行に2兆円の公的資金を注入して実質国有化するまで、くすぶり続けました。この間に、100を超える金融機関が破綻し、100兆円以上が不良債権処理に投じられ、日本経済回復の大きな足かせになったことは言うまでもありません。日本の平成金融危機は、歴史に残る金融危機であり、その時代を生きた私たちそれぞれの人生に、大きな影響を及ぼしました。
■金融危機のリスクは常に存在すると考えるべき
こうした金融危機の教訓は、経済学の発展も相まって、その後の危機のハンドリングにも大きく活かされています。2008年にアメリカで起きたリーマンショックでは、信用不安を和らげるために銀行への大規模な資本注入が早い段階で実施されると共に、金利引き下げだけでなく量的な金融緩和や、中央銀行間の外貨融通など、様々な手段が講じられ、その影響を多少でも小さく、短くすることに貢献しました(それでも影響は甚大でしたが)。
しかし、資本主義や市場経済が続く限り、金融危機のリスクをゼロにすることはできないでしょう。景気が過熱から後退へと移る局面では、常に、そのリスクがあると言って良いでしょう。景気が良いときに発生した過剰な投資や融資が、経済状況の悪化で回らなくなり、それが経済主体の破綻につながります。いわば普通に発生する事象です。これが企業単体ではなく、あるセクターで大規模に起きれば、いわゆる「○○バブル崩壊」という現象になり、この「バブル崩壊」が「金融システム全体」に影響を及ぼすようになれば、「金融危機」につながることになります。
いったん金融危機になれば、「信用」による貸し借りが、通常の時のようには行えなくなるので、危機とは無縁だった経済主体にも、経済の血液である資金が回らなくなる可能性があり、経済全体への影響が甚大になります。経済全体が悪化すれば、金融機関はさらに大きな痛みを被り、金融危機が一層深まるという「負のスパイラル」に陥りかねません。これが、私たちが平成金融危機から学んだ教訓です。
■急激な金融引き締めで、世界的危機のリスク
翻って、今の世界経済を見れば、リスクが相当高くなってきているように見えます。歴史的に見れば、アメリカが金融引き締めに転じた時は要注意なのです。しかも今回は、0.75%という「3倍速利上げ」を連続で行うほどの急激な利上げで、ドルの借入れコストは急騰しています。その一方、引き締め直前までは、コロナ危機対応のために、金融はゼロ金利に量的緩和、財政も大盤振る舞いと、アメリカ国内だけでなく世界中にお金がばらまかれています。
この間にドル借り入れを急増させた新興国や、信用リスクの高いセクターや企業、最近になって生み出された資金調達手段や金融商品など、注意を要するところはいくらでもありそうです。しかし、危機がどこで起きるかを未然に特定することは至難の業です。そもそも危機は起きてみないとわかりませんし、LTCM危機の時の「ヘッジファンド」や、リーマン危機の時の「サブプライムローン」のように、その時々の時代と状況によって、「主役」になるものが異なってくるからです。先日、暗号資産(仮想通貨)交換業者FTXでの取り付け騒ぎや破綻劇も、新しいタイプのリスクで、ひょっとしたら、これらにも金融危機の芽が含まれているかもしれません。
平成の金融危機から25年が経ち、この間、そのツケに苦闘した日本経済の歩みに思いを巡らすと共に、金融危機への備えに不断に取り組む必要性を改めて感じざるを得ません。
播摩 卓士(BS-TBS「BiZスクエア」メインキャスター)