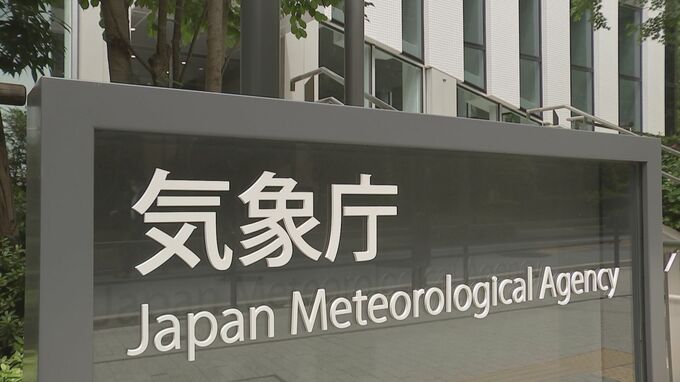気象庁は27日、全国各地の気象台などで行ってきた、初霜と初氷の観測を、2025年度の冬のシーズンから取りやめることを明らかにしました。
初霜と初氷の観測は、全国の気象台や測候所で、植物や地面についた霜や、屋外に設置した結氷皿に張った水が凍っているかを職員が目視で行ってきました。
長野県内では、長野、松本、諏訪、軽井沢、飯田の5つの地点で観測が行われていましたが、現在は、長野のみで行われていて、例えば長野では、1890年の10月14日に初霜が観測されて以降毎年、初氷については1925年の10月26日に観測されて以降毎年の記録が残っています。
気象庁では、近年、アメダスや気象衛星などの最新の観測技術によって、客観的な面的気象情報を全国を網羅する形で提供出来るようになってきていることに加え、霜注意報や低温注意報の利用が進んできているとして、この冬のシーズンからは、目視による初霜や初氷の観測を取りやめることにしたとしています。
すでに自動化されている初雪や、長野地方気象台が目視で行っている東方連山の初冠雪の観測は、この冬も行われます。

気象台の職員による生物季節観測も、2021年1月に、桜やあじさい、すすきの開花などを残して廃止されていて、快晴や薄曇りと言った天気や、黄砂やひょう、降灰などの大気現象の職員の目視による観測については、東京と大阪を除いて2024年3月で終了し、自動化されています。