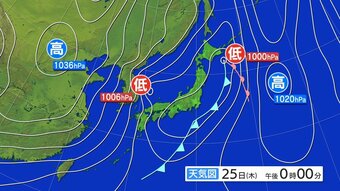岩手県軽米町で、ビールの原料になるホップの収穫が最盛期を迎えています。収穫の現場を取材しました。
岩手県はホップの生産量が日本一です。軽米町、岩手町、二戸市、おとなり青森県の三戸町、田子町の五つの市と町で構成する岩手県北ホップ生産農業組合も一大産地です。
軽米町のホップ畑でも今週から本格的な収穫が始まり今、最盛期を迎えています。
(ホップ生産者・中里照夫さん)
「もう水分不足でよくて平年作までいければいいかな」
軽米町でホップの栽培が始まったのが1962年。中里照夫さんも40年以上ホップ作りに携わり、大切に育ててきました。ホップはツル性の多年草でその寿命はなんと30年以上。冷涼な県北の気候が栽培に適しています。収穫するのは毬花(まりばな)と呼ばれる部分で5.5メートルまで高く伸びたツルと一緒に刈り取りトラックに積んでいきます。
(中里照夫さん)
「圃場班と言いまして、2班あるんですけども(全員で)30人。トラックの荷台に乗って高所作業台に乗って上を刈り取る人(ホップが)はみ出さないように積み込む人ツルの根元を切る人そういう風に分かれていました」
ホップは主にビールの原料に使用され、香りや苦みのもとになります。その成分が含まれるのが、この黄色く小さい粒「ルプリン」です。今年は水不足により生育が心配されましたが8月上旬のまとまった雨のおかげで品質は上々。
収穫したホップは、すぐに処理加工センターへ運ばれます。ここで、ホップの華やかな香りを閉じ込めるためペレットに加工します。加工したホップは全国のビール工場へ、そして余ったツルや葉も無駄にはなりません。
(ホップ生産者・長井昭洋さん)
「ツルは普通はごみになるがそれをたい肥にして(栽培に使う)糸も畑に戻しても自然に分解されて自然に返るようなものを使ってというような循環でやってます」
最盛期は町内に140ヘクタールあったホップ畑も現在は20ヘクタールほどになり、生産者も高齢化などを理由に減少を続け担い手不足が課題となっています。そんななか、中里さんの畑には若い男性の姿も。息子の直人さんです。
(中里直人さん)
「一番は父がやっていたのでそれを身近に見ていたのがきっかけですね軽米町の特産であるのもあってやりたいと思いました」
ホップ作りに携わるようになってことしで7年目の直人さん。父の横で栽培のノウハウを勉強中です。
(中里直人さん)
「ほとんどが手作業なので機械が使えないのが大変。その分手をかけてきれいに作ることができるのでその辺は楽しい」
岩手県は国内1位のホップの生産地ですが自給率は5%未満と大変低く国産ホップはとても貴重です。
(中里直人さん)
「とにかく仲間がいない。少しでも若い人たちもホップ栽培に興味を持っていただいて一緒にやっていってくれればそれが希望ですね」
ホップの収穫は、8月いっぱい続き10月下旬ごろにことしのホップを使ったビールが店頭に並びます。