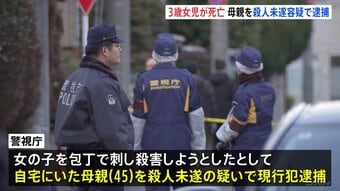戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。原爆が落とされた広島に、爆心地から離れていたのに原爆で様子が一変した村があります。苦難の人生を歩むことになった住民たちを取材しました。
広島の爆心地から10キロ離れた旧川内村で、戦後まもなく撮影された写真。女性や子どもが多いことが分かります。爆心地から離れた村で何があったのでしょうか。
平和公園のある慰霊碑を訪れた横丸正義さん(94)。
横丸正義さん
「(Q.お父様はどちらに?)これです」
原爆で父の正留さんを亡くしました。
横丸正義さん
「この辺にお寺があって、そこへ弁当を置いて仕事をしよったらしいです。家をめいで(壊して)、木を除ける」
当時、広島では空襲による火災の延焼を防ぐため、建物を壊しておく「建物疎開」の作業が市内各地で行われていました。あの日、横丸さんの父親ら川内村の人たちは、国民義勇隊として爆心地近くでの建物疎開に従事していたのです。
横丸正義さん
「多いのう」
働き盛りの男性など、200人近くの命が一瞬にして奪われました。
横丸正義さん
「(Q.お骨は?)結局、どこにどうなったか分からない」
母・露子さんも正留さんを捜しましたが、見つからなかったといいます。
同じように一家の大黒柱だった夫を亡くした村の女性は、およそ70人といわれています。子どもと共に残された女性たちは、苦しい生活を強いられました。
横丸正義さん
「米や麦を収穫する時には、夜9時頃にはまだ田んぼの中にいる。仕事に一生懸命だった。子ども養わないといけないから」
40年前、JNNが川内の夫を失った女性たちを取材した映像が残っています。当時83歳の高崎ハルさん。残された女性たちで励ましあっていたといいます。
原爆で夫を亡くした高崎ハルさん(当時83)
「海行って『おとうさーん』とみんな言いなさいって言って、家でそのように大きい声できないから。いろんなことで慰めあったり」
原爆投下の翌月から行われている月命日の法要の場でも、お互いを励ましあってきました。法要は80年引き継がれ、今の住職が三代目。年々参加する人が減っているといいます。
浄行寺住職 坂山厚さん(76)
「だんだん、だんだん(当事者が)亡くなっていくなと。これからも何とかこれを聞いて、残していかなきゃいけないな」
戦後80年。被爆者、そしてその家族の思いは、戦後生まれの私達の世代が引き継いでいかなくてはなりません。
注目の記事
「戦後最短」真冬の選挙戦 消費税減税でほとんどの各党“横並び”物価高に有効か?「食料品の消費税ゼロ」飲食店の困惑 穴埋め財源も不透明のまま…【サンデーモーニング】

“働いても働いても”…抜け出せない過酷な貧困 非正規雇用890万人 30年で広がった格差社会 政治の責任は?【報道特集】

衆議院選挙 序盤の最新情勢を徹底解説 自民「単独過半数」うかがう勢い 一方で中道は大幅減か・・・結果左右する「公明票」の行方とは【edge23】

今季も驚き“ニセコ価格”カツカレー3000円でも利益は180円、VIPに人気のケータリング1回30万円でも“安い”ワケ…北海道民には遠いリゾートの経済の仕組み

5年前は部員3人「声を出すのが恥ずかしく⋯」センバツ初出場・高知農業、21世紀枠で掴んだ“夢舞台”への切符【選抜高校野球2026】

政策アンケート全文掲載【衆議院選挙2026】