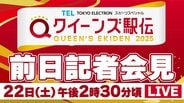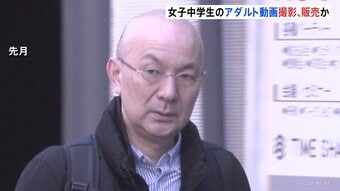日本人初の13秒台から36年で、日本の110mハードルが12秒台へ
日本人初の13秒台(13秒95)を1989年に出したのは岩崎利彦(当時順天堂大)だった。岩崎は富士通入社後に3度も日本記録を更新し、91年には13秒58まで縮めた。岩崎が13秒58を出した場所は旧国立競技場で、34年前の東京世界陸上だった。岩崎の実績は順天堂大の後輩である泉谷と村竹が、9月の東京2025世界陸上に臨むときの後押しとなるだろう。
その後日本記録を更新できない期間が生じたが、99年に谷川聡(当時ミズノ)が13秒55をマーク。内藤真人(当時ミズノ)が2度更新して13秒47と初めて13秒50を切ると、04年には谷川が13秒39まで縮めた。
その記録が14年間残り続けたが、18年に金井大旺(当時福井県スポーツ協会)が13秒36と更新すると、金井、高山峻野(30、ゼンリン)、泉谷(当時順天堂大)の3人が日本記録を更新する期間が続いた。19年に高山が13秒25と初の13秒2台を、21年には金井が13秒16と初の13秒1台を、同じ21年には泉谷が13秒06と初の13秒0台を記録した。
13秒1台を世界陸上や五輪の準決勝で出せば、決勝に進出できる。3人が日本新の応酬をすることで日本の110mハードルは世界トップレベルに成長し、23年の世界陸上ブダペストではついに、泉谷が決勝進出を果たして5位と、五輪&世界陸上で日本人初の入賞を成し遂げた。
そこに登場してきたのが村竹である。泉谷が23年6月に出した13秒04の日本記録に、その年の9月に村竹(当時順天堂大4年)も13秒04を出して並んでみせた。そして村竹は翌24年のパリ五輪5位と、前年の世界陸上の泉谷に続き日本人初の五輪入賞を達成した。
村竹自身はいつ頃から12秒を意識し、どのように手応えを感じながら今回の快挙に至ったのだろうか。
「12秒台をちゃんと見据えるようになったのは、大学4年の日本インカレで13秒04が出た時です。翌年(24年)の日本選手権の準決勝もすごく良い感覚で、リラックスして余裕も持てて、それでも(向かい風1.0mでも)13秒14で走ることができました。決勝は12秒台は出せませんでしたが、2年続けて13秒0台(13秒07)を出せたことで実力を再確認できたんです。欲を言えばパリ五輪で12秒台を出したいと思っていましたが、上手くいかず、今年にしっかりつなげようという思いで冬期練習をやってきました。今年は12秒台を狙った大会が5月のゴールデングランプリでしたね。国立競技場で出すことができたら、同じ場所で行われる世界陸上に向けて大きい自信につながると思ったのですが、意気込みすぎて(優勝したが13秒16と)上手くいきませんでした。しかし6月のダイヤモンドリーグ・パリ大会で13秒0台を2本(2本とも13秒08)、短いスパンで出すことができて大きな自信になりましたし、7月のダイヤモンドリーグ・モナコ大会(13秒17で4位)の後は2週間と短い期間ですが鍛錬期を設けて、12秒台を見据えて今日のレースができました」
岩崎の13秒95から36年。日本人初の12秒台はこうして誕生した。