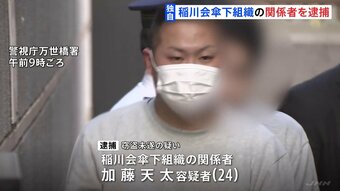登壇した当事者たちの声「子供を生むことの意味」
一方、AIDで生まれた別の登壇者は、9歳と小さいころに告知されたこともあり、思い悩むことはなかったそうです。ただ、教育に関心を持ち、その分野の研究者を目指しているのは、AIDで生まれたことと無関係ではないだろうということです。
この日は「子供を生む」ということをどう考えるか、について、自身の考えを話しました。
AIDで生まれた登壇者
「強調しておきたいのは、子供は親の自己実現の手段でもないし、社会を維持するための資本でもないということで、親になる権利だったりとか、社会のインフラの都合だったりとか、そういうものよりも、生まれてくる子供の幸福が大事に考えられる社会を望んでいます。こうして注目をいただいてるからこそ、子供を作るっていうことそのものの重みっていうのが、いま一度、問い直されてもいいのかなと考えています」
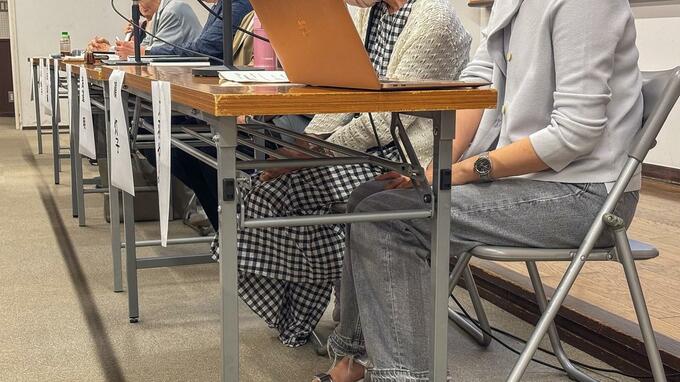
AIDで子供を持った人も原稿を寄せています。
自身が無精子症で、現在6歳ともうすぐ2歳になる娘がいる父親が登壇し「私の今回の本の内容としましては、無精子と向き合いながら、夫婦で悩み、そして考え、時には本当に大げんかをしながらですね、この選択肢を選んで、ようやく生まれた私達の家族の物語について、書かせていただきました。私達は子供に隠さない、そして子供に恥じない選択をしていこうということを大事にして血のつながりよりも、どう向き合い、どう子供を育むかということをずっと大事にしていまして、それを信じています」と話し始めました。
「隠さない」ということで、お腹の中の赤ちゃんに話しかけるところから始め、AIDで生まれたことを子供にずっと伝え続けているそうです。また、「AID当事者支援会」という、同じように悩む人の居場所を運営しています。
「出自を知る権利」を保障する法や制度はないまま
どの登壇者も、精子を提供した第三者が誰か、知るすべはありません。先の国会では、第三者の精子や卵子の提供で生まれた子供の「出自を知る権利」の保障を含む法案が出されました。ただ、法案を作る過程で、当事者が意見を聞かれることはありませんでした。
法案でも開示される情報が少なく、様々な当事者が求めている情報とは異なり、また、開示される情報以上のものを求めても、それをする・しないは提供者の同意が必要であるなど、当事者にとっては不十分なもので、結局廃案となりました。
この日登壇した中には、AIDで生まれた人がパートナー、という人もいました。本に原稿は寄せていますが、パートナー以外の当事者たちと直接会うのは初めてだったそうです。
パートナーとの向き合い、自分たちの子供にどうそれを伝えるか、また、AIDについて考えてきたことを様々に語りましたが、最後に本や出版記念イベントについて「この本には1人1人の人生が、1人1人の思いが詰まっているので、ぜひとも皆さんこれ読んでいただいて、当事者の気持ちとかも十分に理解していただいて、またこういう会に参加していただければなと思っています。すごく議論っていうのは大切だと思うので、これまでタブー視されてきたことも、こうやって立場が違う人たちが集まって、これからもやっぱり議論していくってことはとても大切だと思うので、こういう機会、本当に持ててよかったなと思います」と話しました。

当事者の声を聞き、AIDなど生殖補助医療について考えるきっかけに
この本には他に、かつて精子を提供したことがある人と、AIDで生まれた人たちの座談会の記録など、考えるきっかけが詰まっています。
生まれてくる子供たちにとって、どうすることが一番の幸せにつながるのか、社会の誰もが無縁ではありません。AIDだけでなく、法や制度などの明確なルールがないまま行われてきている、その他の生殖補助医療について考えることにもつながるでしょう。
(TBSラジオ「人権TODAY」担当:崎山敏也)