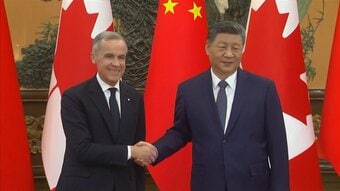狙いはアジア20億人市場。インバウンド戦略の勝算は?
野村:
宿泊を促すということは、メインターゲットは県外、特に海外からの観光客になりそうですね。
comugi:
ジャングリア沖縄の運営を支援する株式会社刀の森岡毅氏は、年間来場者数のターゲットを100万人から150万人程度と示唆しており、沖縄県の人口は約146万人ですから、国内需要だけでは目標達成は困難です。
これは年間1000万人が訪れる沖縄の観光客、特にインバウンド(訪日外国人旅行客)の取り込みが不可欠であることを意味します。
森岡氏は「沖縄から飛行機で4時間圏内には、中国やASEAN諸国を含め20億人以上が住んでいる」と述べており、この巨大なアジア市場を明確にターゲットとして見据えています。
野村:
20億人市場ですか。その狙いは当たりそうなのでしょうか。
comugi:
ここが、期待とともにいくつかの不安要素が見えてくるところです。
成功への懸念1:「1時間に何人さばけるか?」オペレーションという見えざる落とし穴
野村:
不安要素というと、具体的には何でしょうか?
comugi:
ひとつは「オペレーション」、つまり「1時間あたりにどれだけのお客さんをさばけるか」という問題です。実は、刀が以前プロデュースを手がけた「ネスタリゾート神戸」の口コミを分析すると、運営面での課題が浮き彫りになります。
ジップラインやカヌーといった大自然系のアトラクションは、一度に体験できる人数が少ないため、どうしても待ち時間が長くなる傾向があります。
ジャングリアの「4人乗り巨大ブランコ」や「12人乗りオフロード車」も同様の構造を持っており、人気が出れば出るほど長い行列ができ、顧客満足度の低下に直結しかねません。
野村:
なるほど。テーマパークの成功事例とは異なる構造なのですね。
comugi:
例えば、東京ディズニーリゾートのアトラクションは、機械制御によって乗り物が次々と動き、1時間あたり1000人単位のゲストを処理できるものも少なくありません。
また、ジャングリアのすぐ近くにある「美ら海水族館」は、お客さんが自分のペースで歩いて観覧する「ウォークスルー型」です。そのため、館内がどれだけ混雑していても人の流れは止まらず、年間300万~400万人という膨大な数の来場者を受け入れることが可能です。
これらに対し、ジャングリアの体験型アトラクションは、その構造上、どうしても処理能力に限界があります。一つ一つのアトラクションがどれだけ魅力的でも、このオペレーションという命綱が、ゲストの評価を左右する大きなポイントになるでしょう。