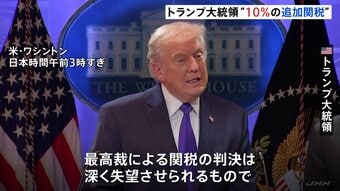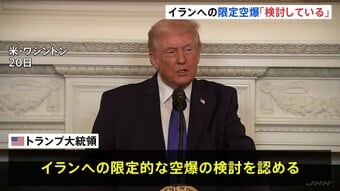生きづらさに向き合う。“最適”という答え
作品を通して伝えたいことを尋ねてみると、富士屋氏は少し考え込みながら、静かに言葉を選んだ。
「うまく言葉にできないのですが、生きづらいと感じる人って、理想を追い求め過ぎているところがあると思うんです。全てを完璧にしようとせず、あえて諦めることも必要。自分の役割の中で“折り合い”をつけていくことで、社会とのずれを合わせる。それって、“最適”を探っていく総合診療科の考え方にも通じるものがあると思うんです」。
“最適”は、最良とは違う。100点満点ではなく、その人にとって一番合った答えを見つけていくこと。医療も人生も、結局は「こうすべき」よりも「これでいい」と納得できる地点に近づけていくプロセスなのかもしれない。
「僕自身、全部がうまくいっている人間ではないんです。うまくいかない中で、何を選ぶか、どう折り合いをつけるかを考えてきた。その気持ちを登場人物たちに投影しているところがあると思います」。
病気の診断や治療だけではなく、患者の「人生そのもの」に寄り添う総合診療科という存在。そんな医師たちのまなざしと、作者自身の人生観が、作品の根底で静かにつながっている。

総合診療というテーマに向き合いながら、どこか生き方にもリンクするような普遍性を描き出す富士屋氏ならではの視点。それが、「19番目のカルテ 徳重晃の問診」という作品の優しさと温かさを生んでいる。