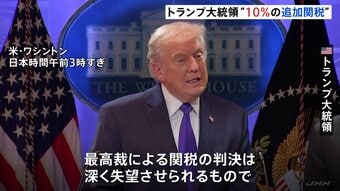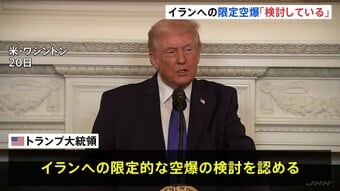専門分化が進む現代医療において、あらゆる症状の“入り口”として注目されるのが「19番目の新領域」ともされる「総合診療科」だ。年齢や性別、臓器にとらわれず、患者を“人”として診る――そんな医師たちの姿を描く漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』(ゼノンコミックス/コアミックス)は、現在も連載が続く話題作である。
本作を手がけるのは、『しょせん他人事ですから〜とある弁護士の本音の仕事〜』(白泉社)などの作画を担当している富士屋カツヒト氏。本作には、医療現場のリアルと、登場人物たちの丁寧な人間描写が織り込まれている。
なぜこのテーマに挑み、どのようにキャラクターを立ち上げていったのか。物語の舞台裏を、富士屋氏に聞いた。
“人を診る医師”のリアルを追って
作品誕生のきっかけは、編集部から「“総合診療医”という企画で描いてみませんか?」と声をかけられたことだったという。当初、富士屋氏はその“総合診療医”という言葉にすぐピンときたわけではなかった。
「当時NHKで放送していた『総合診療医ドクターG』という番組でなんとなく知っている程度で、他の専門医とどう違うのか、はっきりとは分からなかったんです」と振り返る。
主人公で総合診療医の徳重晃を作っていく中で、医療原案として本作に協力している現役の総合診療医として活躍中の川下剛史医師の話が大きな助けになったという。総合診療科はさまざまな専門科と連携しながら診療を行う。そのため、他の医師や診療科の特性を把握し、尊重することが欠かせない。
富士屋氏は「医療現場にいる人目線の話の数々を聞いていて、その人しか見ることができないアングルに面白さを感じました」と明かす。
そんな川下医師からの監修コメントには、専門領域の医師たちに対する敬意が随所ににじむ。「『この表現は変えたい』といった指摘の1つ1つに、“なるほど”と目から鱗が落ちるような視点があって。とても勉強になりました」と富士屋氏は振り返る。