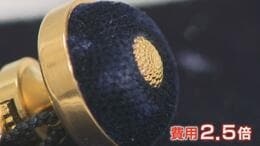全ての話に“自分”がいる

徳重ら医師たちの人物像や診療エピソードは、川下医師から聞いた話から着想を得ながら丁寧に作られていった。一方で、作中で徳重のもとを訪れる患者たちは、富士屋氏自身の“視点”を色濃く反映して描いている。
「川下先生からは“医療現場の温度感”を教えてもらい、患者の描写には、常に“自分の物差し”を持ち込んで描いています」。
例えば、第7巻で描かれる“真夏の公園で徳重が出会ったヤングケアラーの少年”、第8巻で描かれる“母娘による老老介護”や、第9巻で描かれる“ワンオペ育児に追い込まれた父親が気づけなかった子どものくる病”など、家庭や暮らしの中でこぼれ落ちていきそうな声に光を当てる回には、とりわけ力が入ったという。
「妻がもし入院したらどうなるだろう、自分がもしワンオペすることになったら…と、描く際には自然と自分を重ねてしまうんです。どの患者のエピソードにも“自分がいる”感じがしています」(富士屋氏)。担当編集者も「常に“当事者の視点”で描こうとしている点が印象的です」と語る。
そっと寄り添う物語と、愛されるキャラクターたち

富士屋氏が特にこだわっているのは、“余韻のある終わり方”だという。日曜劇場『19番目のカルテ』の第2話でも取り上げられたヤングケアラーの回は、1コマ1コマに余韻を感じることができる。
「漫画では“完治”よりも“関係性”を描きたかったんです。徳重がそっとその少年の隣にいることで、また困った時に戻ってこられるような…そんな“ご縁”を残したかった」。徳重が少年にさりげなく寄り添っていることを示す、小道具として描かれたタクシーの領収書。その1コマにも、富士屋氏の思いがにじむ。
キャラクター造形も、1つ1つ丁寧に組み立てている。その象徴的な存在が、徳重に感化され整形外科から総合診療科に転科した若手医師・滝野みずき。モデルとなったのは、富士屋氏がかつてバイト先で出会った大学生だった。
「ツヤのある黒髪が印象的な、真っすぐで元気な子で。徳重がちょっとふわっとしているキャラクターだったので、対照的に見せたかったんです。滝野は真面目で一生懸命な“学級委員長タイプ”。それだけだと堅く見えかねないので、読者が応援したくなるような“愛される若者”として描きたいと考えました」。
そんな滝野について「不思議な魅力があるキャラクター」と富士屋氏。「周りの感想を聞くと、滝野は実際は強い人間なのに、どこか放っておけないような人を惹きつける魅力があるんです。そういうふうに捉えることができるんだなと驚きました。僕にとっては描きやすいキャラクターなんですけどね(笑)」と語る。