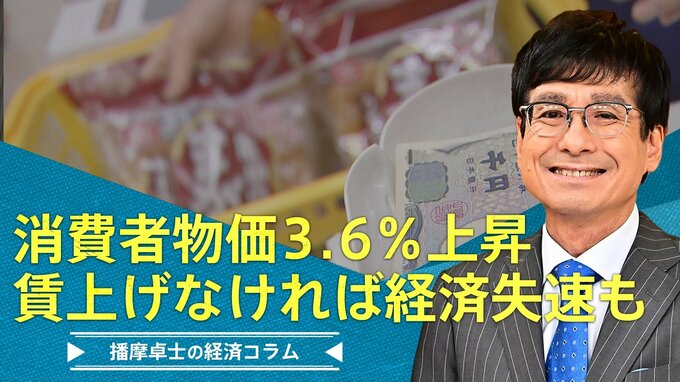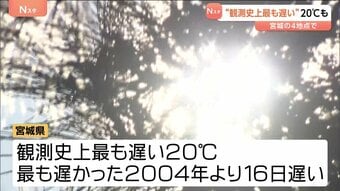10月の全国の消費者物価は、生鮮食品を除いた総合指数が前年同月比で3.6%の上昇と、1982年2月以来、40年8か月ぶりの大幅な上昇となりました。これまで「何年ぶり」と原稿を書く際には、「消費税増税時を除くと」という但し書きをつけるのが通例でしたが、今回は消費税導入時(1989年)や、5%から8%への増税時(2014年)を上回り、正真正銘の40年ぶりの物価高です。
40年ぶりと言えば、私個人にとっても、バブル期を含めて社会人になって最も高いインフレを経験していることになり、私たち日本国民は、まさに歴史的な物価高に直面していると言っていいでしょう。
■物価上昇は「想定以上」に高く、広く
10月は食料品を中心に値上げした商品点数が多く、インフレ加速が懸念されていましたが、9月の3.0%上昇から一気に3.6%へと、政府・日銀の想定以上の急上昇です。内容を見ると、食料が6.2%、エネルギーが15.2%と変わらず物価上昇の中心ですが、急激に進んだ円安と価格転嫁の進展で、上昇率そのものが当初の想定以上に高くなっています。
また、物価上昇が、食料やエネルギーに留まらず、家電製品をはじめとする耐久財など、想定以上に幅広いモノに広がってきています。日銀が重視する生鮮食品とエネルギーを除くコア指数でも、10月は2.5%上昇と、日銀が掲げる「2%の物価目標」を始めて超えており、その広がりが確認できます。
10月は全国旅行支援が始まり、宿泊費が前年同月比で10.0%も大幅下落するという特殊要因がありました。補助金のおかげで実際に消費者が支払う宿泊代金が安くなったわけです。総務省によれば、全国旅行支援の寄与度はマイナス0.17%だということで、この特殊要因を除けば、消費者物価はその分だけ、より上がっていたことになります。生活実感に近い、生鮮食品なども入れれば、私たちはすでに4%近い物価上昇を体験していることになります。
■実質賃金はマイナスで、消費は生活防衛的に
その一方、賃金は物価上昇に全く追いついていません。毎月勤労統計によれば、9月の実質賃金はマイナス1.3%で6か月連続のマイナスです。10月のデータはまだ出ていませんが、引き続きマイナスでしょう。こうした状況が長く続けば、消費が落ちない訳がありません。足下、この秋の日本経済は、コロナ感染が落ち着き、外出、外食、旅行などが活性化し、いわゆる「リベンジ消費」で消費は底堅く推移しているようです。しかし、「リベンジ」が一巡し、賃金が上がらなければ、消費は急速に冷え込むことでしょう。
日銀は、現在の物価上昇は、サービス価格には広がっておらず、輸入材のコスト上昇による「一時的な」もので、来年には落ち着いていくと想定しています。本当に日銀の「想定通り」になるのかどうか、答えはまだわかりませんが、一つ確かなことは、欧米と違って、長く「デフレ時代」を経験した日本経済は、物価上昇への耐性が極めて弱いということです。
40年ぶりの物価上昇に直面すれば、生活防衛意識は急速に強くなるでしょう。小売り大手が安売り商品に力を入れるなど、すでにその兆しはあちこちにみられます。そもそも「2%の物価目標」が日本には高すぎるという見方もあり、欧米と比較して「インフレはマイルドだ」といった楽観論は戒められるべきでしょう。
■円安メリットも生かせず…景気失速の恐れも
本来なら、円安のメリットを受ける輸出やインバウンドが、日本経済をけん引することが期待されるところですが、生産の海外移転や国際競争力の低下もあって、輸出数量は、今でさえ伸びていません。2023年の世界経済は、欧米の急速な金融引き締めを受けて景気後退局面を迎えそうで、日本経済は、その影響を一際大きく受けそうです。インバウンドも、中国のゼロコロナ政策の影響で、いまだ本格的に立ち上がっていません。
今後の賃上げを決める春闘は、そうした微妙な時期に行われることになります。物価上昇を上回る大幅な賃上げの実現は、なかなか難しそうな気配です。今の物価上昇を日本経済の前向きな好循環につなげるとためには、大幅な賃上げが欠かせません。政府も中央銀行も、企業も労働組合も、そうした認識を共有する必要があります。その挑戦が失敗に終われば、日本経済は、好循環実現への、千載一遇のチャンスを逃すことになりかねません。
播摩卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)