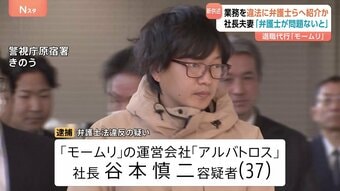参議院選挙の結果は与党惨敗、参政党と国民民主党の躍進という展開となりました。なぜこのような結果になったのか、そしてこれからの日本政治はどう動くのか。政治の最前線を共同通信特別編集委員の久江雅彦さんにききました。(聞き手:川戸恵子 収録:7月24日)

50代が分岐点 二分される情報接触ツール
ーー今回の参院選での投票先を年代別にしたものですが、ご覧になっていかがですか?
共同通信 特別編集委員 久江雅彦氏:
今回の選挙を見事に象徴している図ですね。20代、30代を見てもらえばわかりますけども国民民主党、参政党が多いですね。40代ぐらいからやや微妙になってきて50代と。
これ、実はいわゆる日本国民がどこから政治の情報を得ているのかというグラフと符号するんですね。40代以下は、テレビや新聞よりも、インターネット、SNS、そこから情報を取る人が若くなればなるほど多くなるんです。逆に50代を分岐点として、年配になればなるほど、ネットよりもテレビ・新聞なんですね。

振り返ってみますと国民民主党は「手取りを増やす夏」、参政党は「日本人ファースト」。ある意味過激な部分とか鋭角的な主張。これがショート動画や、あるいはSNSでバズるわけですよ。
他方、自民党や立憲民主党のように、あれもやりますこれもやりますっていうファミレスというか総合デパートというか。結局SNSとかネットの特性では、全然バズらないんですよ。一点集中で鋭角的に単品料理でどんと出すのがバズりやすい。
参政党の求心ということで言えば7月3日の公示以降ですね、いわゆる国会議員が5人になって、地上波含めて一般の旧来メディアにも出るようになりましたね。
そうしますと50代より年配の方にも参政党ってのがあるんだって、こっちの層にも見せるわけですよ。テレビに出たよっていうことが、またネットにも出るっていうことで相乗、雪だるまのようになっていくと。だから今国民はその政治を見ているまでが大きく二つあるっていうことが、この図から如実にわかるわけですよね。
深読みするとですね、都議選もそうですし、今回の参議院選挙もいわゆる公明党であるとか共産党であるとか、旧来、強い組織票があったところが相当票を減らしてますよね。人口減とはいっても新しい有権者が増えてくるわけですから、その人たちが既存政党にいくかというとそうではなくて、それを主にネットが拾ってるという。