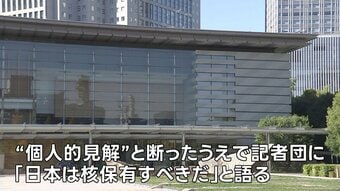「しあわせは食べて寝て待て」の<団地>
影山 「しあわせは食べて寝て待て」(NHK)にいきましょう。
倉田 物語のテンポ感がすきです。日々せわしないじゃないですか、みんな忙しくて時間に追われている。そういう中で、桜井ユキさん演じる主人公は膠原病になってしまい、大手の会社をやめ、小さなところで休みも多めに取りながら働く。給料が減ったので、家賃の安い団地に引っ越して、そこで薬膳と出会い、近所の人とも交流しながら日々を過ごしていく。その様子が描かれるんですが、主人公のような生活を私が今できているかというと、全くできてない。
私は先日、体調を崩して二週間ぐらい休んだんです。思うように働けない時間を持つことになって、何となく主人公に肩入れしてしまいました。いろいろな事情を抱える中で、働くというのはどういうことなのかも結構考えさせられました。
主人公は自身の体調や状況に合わせて、仕事や住む場所を選び取っていきます。私のこれまでの生き方はそうじゃなくて、仕事のペース最優先で、そっちに自分を合わせていました。でも、それとは違う、今の自分を中心に周りの状況を変えていく生き方もあるんだと教えてくれた作品でした。
団地というのがいい舞台です。小泉今日子さんと小林聡美さんの「団地のふたり」(NHKBS・2024)というのがありましたけれど、戦後の昭和時代を感じさせます。ゆったりした時間が流れていそうなイメージそのままの暮らしが描かれていて、ご近所さんとの交流もあって、忙し過ぎる現代人には憧れの生活だと感じました。
田幸 一方、団地への憧れがありつつ、団地の老朽化問題がやっぱり出てくる。いいな、あんなところで老後を過ごしたいなというだけでなく、老朽化、取り壊し、引っ越しの問題に目を向け、おとぎ話にしてしまわない。現実の厳しさもシビアに描いている。優しい温かい世界と、お金や、いろいろ新陳代謝していかざるを得ない厳しい現実を描いているのが、いかにも今のドラマだなと思います。
「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉がこの作品に出てきます。容易に答えの出ない事態に耐え得る能力のことを言うそうです。どう頑張ってもできないことがある時に、それをどう乗り越えるかではなく、できないことはできないまま受け入れて、そこからどうしようかと考える。私たちの日常の中でも、ヒントになる言葉だと感じました。
あと、膠原病の主人公は、はたから見るとどこが悪いのかわからない。外から見ただけではわからない痛みを抱えている人もいるということを覚えておこうと思います。見えない人の痛みにも、できるだけ敏感でありたいと感じました。
影山 ちょっと違う角度で言えば、おとぎ話ではないという点に賛同はしますが、じゃ、現実的なドラマかというとそうでもない。私たち見る者にささやかな夢を見させてくれるというか、本当は無理だけど、そういうのがあるといいよねというささやかな願望。
現実はどうかというと、僕も例外ではないですが、マンション住まいで、お隣りとはできるだけかかわらないように無意識に選択している。その一方で、このドラマのような関係性に憧れている。ないものねだりなんですね。たとえば宮沢氷魚さんみたいなご近所さんは現実にはいなくて、逆にあのトーンでお隣さんが寄ってきたら気持ち悪いですよね。
田幸 怖いですね。
影山 もちろん氷魚君には邪心がなくて、心を許すというか、淡い恋愛感情も、という流れではありましたけれど。
いつも言うことですが、リアリティとおとぎ話とのバランスはすごく大事です。絵空事で薄っぺらいと見る者の心は打たないですから。フィクションだけれど、リアリティがあるということが大事ですね。