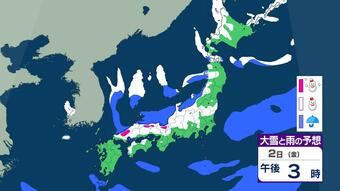秋が深まり、暦の上では冬。「立冬」を過ぎました。そんな中、私がいっそう励んでいるのが「リス活」です。私は小動物全般が大好きですが、なかでもイチオシはリス。子供の頃にシマリスを飼っていたこともあり、幼い頃から今に至るまでずっと好きな動物です。
秋冬シーズンは多種多様なリスグッズが世に出てくる時期です。リスグッズのコレクターである私は、リス関連情報をインターネットやSNSで日々収集しています。まさにこれが、リス活です。さらに、仕事が休みの日にはリスの写真を撮るために、遠方へもあちこちへ行く、リス活をしています。各地の動物園内にいるリスはもちろんですが、野生のリスを探しに北海道まで行くこともあります。今回は、そんなリス話を私の視点で綴りたいと思います。
■シマリスの「SSA行動」 天敵ヘビも撃退する“生きる知恵”
リスの世界は非常に奥が深いと感じます。というのも、一言にリスといっても、実に様々な種類があり、特徴も違います。げっ歯目の中のリス科だけでも300種近くの分類になるとか。
まずはリス科ジリス亜科マーモット族シマリス属のシベリアシマリス。
シマリス属だけでも種類は数十種ありますが、日本で一般的にペットとして飼われているのは中国から輸入されたチョウセンシマリスという種類です。野生のシマリスは、日本では北海道にいるシベリアシマリスの亜種「エゾシマリス」のみです。

ご自慢のほお袋は左右にかなり膨らむ伸縮性があり、たくさんの木の実を詰める姿はなんとも可愛らしい…。耳に毛細血管が集まっているため、暑い日には耳で体温を調節するようです。警戒や緊張をしている時には、しっぽがピンと立ち上がるなど、感情はしっぽに表れます。冬は土の中で冬眠し、その時の体温は5℃程度にまで低下。
それからシマリスは小さいながらも、あるいは小さいからこそというべきか、身を守る術を知っています。「SSA」と名付けられたヘビ避けの行動です。
死んでいたり冬眠しているヘビの皮膚や脱皮したあとの殻をかじって、自分の体に塗り付ける行為をするようです。外敵に捕食されないようにヘビ独特のにおいを自分の体にまとうことで身を守る…生きるための処世術ですね。
環境にもよりますが、シマリスの寿命は6年前後と、とても短いです。私たち人間と比べて10倍以上の速さで時計が進んでいるといった感じでしょうか。そう考えると、一挙一動すべての俊敏さが、愛おしくもなります。