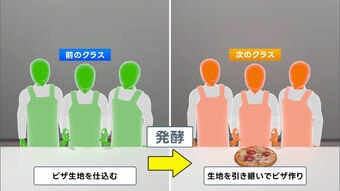日本にとっての「チャンス」
つまり、アメリカでは今、留学であれ、就業であれ、審査は厳格化され、ひと言で言うと排他的な国に変わりつつあり、かつてのような自由で寛容な国というイメージは失われました。そしてこれが今、若年人口の減少とエンジニア不足に悩む日本にとってはチャンスだ、という話が本題です。
コメ問題などであまり大きく報じられませんでしたが、政府は6月4日、「総合科学技術・イノベーション会議」を開き、トップを務める石破首相は「アメリカ政府の政策転換で研究活動に懸念が生じているなか、アメリカを含めた優秀な海外研究者の招聘などを強化する」と表明し、関係閣僚には「海外の研究者受け入れを進めるよう」指示を出しました。
大学側も既に動いており、東北大学が300億円を投じて、国内外のトップレベルの研究者約500人を採用する計画を打ち出したほか、東京大学や大阪大学、広島大学、立命館大学などが受け入れを表明し、九州大学のカーボンニュートラル・エネルギー国際研究所も検討しているそうです。
既にアメリカ側からも、NASA(アメリカ航空宇宙局)をはじめとして、受け入れの問い合わせが来ているといいますが、課題は高額な報酬です。教授クラスだと年間3,000万円を下らないとされ、「国際卓越研究大学」第1号に認定されて政府の支援が受けられる東北大学以外は苦慮しています。
ただ、政府として海外の研究者受け入れを表明しているのですから、研究内容は精査するにしても、国として相応の支援はすべきだと、私は考えます。またもや選挙を前に、国民一人当たり2万円配るとかいう話が出ていますが、実施されれば総額2兆数千億円です。税収が上振れした分を充てると言いますが、それって国民が一生懸命働いた果実でしょう? ならば未来につながる使い方をしないと、報われないと思うんです。
インド人ITエンジニアの可能性
もう一つのチャンスはITエンジニアの獲得。特に注目しているのは、インドの人材です。IMF(国際通貨基金)によると、2025年度のインドの経済成長率は6.2%、GDPはおよそ607兆円に達し、今年にはついに日本を抜いて世界4位になると予測しています。
人口は世界最大のおよそ14億人で、平均年齢は28歳です。14歳以下が4分の1を占める若い国で、モディ首相が2014年の就任以来進めてきたのが「デジタルインディア」政策です。特にIT人材の育成に力を入れ、総合人材サービスのヒューマンリソシア株式会社の調査によると、世界でおよそ3,000万人とされるITエンジニアを国別に見ると、3位は中国のおよそ350万人、2位はアメリカの450万人、そして1位は490万人のインドなんです。
日本は、と言うと、4位の144万人。インドのおよそ3分の1です。前の年からの増加数に至ってはインドが世界一、44万人も増えているのに対して、日本はほぼ横ばいです。
そのIT人材のトップ、上位1%を輩出しているのがインド工科大学(IIT)で、Google CEOのサンダー・ピチャイ氏など、錚々たる名前が上がります。
インド国内の主要都市などに23校を展開し、合わせて10万人ほどが在籍しますが、驚くのはその入試倍率です。IITを受験する前に二つの関門があって、まず、理系の大学を目指す学生が受ける共通テストの志願者が80万人以上、これを通って次の試験に進めるのがおよそ16万人で、この試験を通るのがおよそ4万人。これでようやくIITを受験できるんですが、合格者はおよそ1万6,000人なので、1次試験の志願者数からすると、競争率は50倍以上、合格率はわずか2%です。
それでも多くの若者がIITを目指す背景には、二つの理由があります。一つは収入の高さです。国民の平均年収がおよそ68万円なのに対して、IT人材は5百数十万円。10倍近くです。
そしてもう一つは、カースト=身分制度です。法的には1950年に憲法で廃止されていますが、今も農村部などには根強く残ると言われます。ただ、カースト制度が廃止される前の20世紀初頭もコンピューターはありませんから、ITエンジニアにカーストはなく、能力次第で未来が切り開けるチャンスなんです。まあ、とはいえ難関中の難関で英語力も求められるので、現実には経済力のある家庭でなければ難しいのですが、夢の入り口であるのは間違いありません。