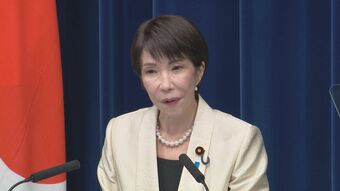社会接触の重要性
政治が「推し活」化していくなかで、従来型の言論中心の政治活動が意味をなさなくなっていくとしたら、何が民主的な合意形成を機能させるために重要なのだろうか。
ルブラノは社会接触だと言うが、私もこの古典的な回答に賛同する。多様な人たちとリアルな友人関係を結ぶということだ。すでに社会接触理論に関する研究では、人々が友人となって協力する条件下では、その新しい友人が属する集団に対する偏見が減少するというエビデンスが積み重なっている。
関係を結んだ人たちとの関わりは偏見を減らし、関心領域を広げ、新しいアイデアを受け入れるための信頼を築く。友人からの間接的な影響力は、見知らぬ人の主張よりも、はるかに大きな効果を発揮するとルブラノは述べている(パラソーシャルとはこの影響関係を想像上の対象に擬似的に形成することである)。
民主主義の健全化のために必要なのは、言葉だけを交わすためのメディアやAIでもなく、何よりリアルな接触であり、それを実現するインフラストラクチャーなのだろう。
注1 柳澤田実「ファンダムの未来はどこにある 「聖なる価値」からその課題と展望を考える」WIRED、 2022年10月17日
注2 柳澤田実「消費社会のカルチャー、ファンダム・カルチャー」『三田評論』オンライン、2024年4月5日
注3 Sarah Stein Lubrano, “This article won’t change your mind. Here’s why,” The Guardian, 5 May 2025
注4 Caroline Le Pennec, “Vote choice formation and minimal effects of TV debates : Evidence from 61 elections in 9 OECD countries, ”Working Paper 26572, National Bureau of Economic Research, December 2019
注5 Dylan Matthews, “Do presidential debates usually matter? Political scientists say no,”TheWashington Post, October 2012
注6 L・フェスティンガーほか『予言がはずれるとき:この世の破滅を予知した現代のある集団を解明する』水野博介訳、勁草書房、1995年。
<執筆者略歴>
柳澤 田実(やなぎさわ・たみ)
関西学院大学神学部准教授。専門は哲学・キリスト教思想。
1973年ニューヨーク生まれ。1996年慶應義塾大学文学部哲学科卒。2004年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。2006年博士(学術:東京大学)。南山大学人文学部准教授を経て、現職。
編著書に『ディスポジション──哲学、倫理、生態心理学からアート、建築まで、領域横断的に世界を捉える方法の創出に向けて』(2008年、現代企画室)、訳書にターニャ・M・ラーマン著「リアル・メイキング いかにして『神』は現実となるのか」(2024年、慶應義塾大学出版会)など。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。